平安時代末期~鎌倉時代前期の武将です。
お父さんは千葉常胤です。お母さんは秩父重弘の娘です。
石橋山で敗走した源頼朝が、安房に上陸し再起をはかった際、頼朝にしたがっています。千葉胤正が、父常胤に対し、頼朝軍への参入を勧めたといいます。
頼朝の寝所を警護する11人の家子に選ばれています。奥州合戦にも従軍しました。
奥州合戦後、藤原泰衡の郎党であった大河兼任の反乱が起きたときは、追討軍の大将軍として平定にあたりました。
頼朝からの信任が厚く、頼朝上洛時、仙洞御所(後白河院)に参上した際には、布衣侍の7名に選出されています。

頼朝軍に参入するように、父ちゃんを説得したのか。

説得したというよりも、なかなか返事をしなかった常胤に「早く早く」とせかしたらしいよ。

安達さんが返事を待ってたから。

頼朝さんにしたがうようにお願いしに来たのはわし。

父の常胤がなかなか返事をしなかったのは、「源義朝に従軍したことがあるため、息子の頼朝が挙兵したことに感極まって泣いていた」という説もあれば、「同族である上総広常に相談したかった」という説もあるよ。

まあ、どっちもだったんだろう。
上総氏の家臣ではないから、千葉氏は千葉氏として参戦を判断すればよろしい。

このへんで、常胤が、頼朝に「鎌倉入り」を勧めたと言われているね。
鎌倉は何より海・山に囲まれた自然の要塞だし、「源氏」の血脈をいっそうアピールするには、源頼義・義家からはじまり、義朝も居住した鎌倉を拠点とするのがいいからね。

「源氏」の氏神としての鶴岡八幡宮もあるしね。

胤正は、頼朝の寝所を警護する11名にも選出されている。
これは「北条時政の息子」とか、「八田知家の息子」とか、いわゆる「二世」的な人材を育成する側面も併せ持った「頼朝親衛隊」のようなものだった。

GO GO 頼朝

頼朝 ヨ リ ト モ

L O V E

YO RI TO MO

まあ、みんながどんなにがんばってもセンターはオレだけどな。

ちっ 義時め。
がんばれ、わしの息子。

わしの息子もがんばれ。

御家人の学芸会みたいになってきたぞ。

この「家子」の11人は、頼朝の身辺警護を主な役割としているから、頼朝が遠征するときは、やはり複数人でついて行って、もろもろのお世話もするんだね。
11人のうちの一人、榛谷重朝なんかは、奥州合戦に際に頼朝の馬を毎日洗ってたって言うからね。
千葉胤正もその例にもれず、頼朝が後白河院に会いに上洛した時は、布衣侍の7名として供奉(儀式や祭礼のときのお供)をしている。

布衣侍ってなんだ?

これは「ほいじ」か「ほいの〇〇」って呼んでたと思う。
布衣っていうのは、官服に対する平服のこと。
貴族が着る服ではなくて、庶民が着る服ということだね。
頼朝が上洛した時に、千葉胤正たちに貴族としての官位官職があるわけではないので、布衣で頼朝の後ろについたということだろうね。

布衣侍の「侍」は「サムライ」って読まないの?

「侍」は「じ」で、動詞なら「はべり」と読むことが多い。または「さぶらふ」。これを「さむらい」と読むのはもうちょっとあとの時代だと思う。
布衣侍の「侍」をなんて読むのかはよくわからないんだけど、意味は「貴人のそばに控える」ということ。
普通に音読みすれば「じ」だから、連続して読むなら「ほいじ」でいいんじゃないかな。
当時は「ある漢字」に対して、わりといろんな読みを「当てる」ことも多いから、「侍」を「かみ」「すけ」「じょう」などと読むこともある。
だから、「ほいの〇〇」という特別な読み方はあったかもしれない。

ヌノギヌザムライじゃないんだな。

たぶん「ほいじ」か「ほいの〇〇」だろうね。
ちなみに、7人というのは、三浦義澄、千葉胤正、工藤祐経、足立遠元、後藤基清、葛西清重、八田知重。

ほい

ほい

ほい

ほい

こうやって、ほいほい言ってついて行ったのかな。

そんなわけではないけれど、メンバー的には大物ぞろいだよね。
千葉胤正も頼朝から相応の扱いをされていたことが分かる。

わしにもあんな付き人たちがほしかった。
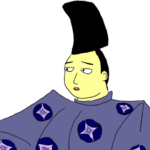
わしも。

そのときの天皇は後鳥羽。上皇が後白河。
後鳥羽は、このときに上洛したメンバーの多くと、のちに承久の乱で対決することになるんだね。
千葉常胤・胤正親子は、頼朝の没後の数年後に逝去しているけれど、千葉氏は代々下総国の守護を務めて、鎌倉幕府を支える有力氏族として活躍していくんだ。

まあ、父ちゃんの功績が大きくて、後世の千葉氏は「胤」の字を使う子孫が多かったよ。


