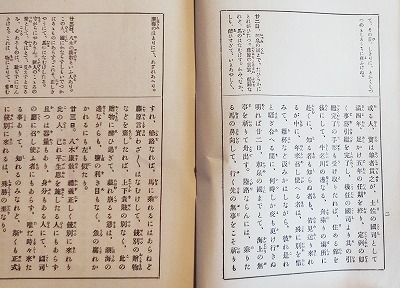〈問〉次の傍線部を現代語訳せよ。
円融院の御はての年、皆人、御服ぬぎなどして、あはれなる事を、おほやけより始めて、院の人も、「花の衣に」などいひけむ世の御事など思ひ出づるに、
枕草子
現代語訳
円融院の喪がお明けになった年、(宮中の)人はみな御喪服を脱ぐなどして、しみじみとしたことを、帝からはじめて、院にお仕えしていた人【女房】も、「花の衣に」などと言ったとかいう御時代のことなどを思い出しているとき、

このあとの話はこちらをどうぞ。
ポイント
御 接頭語
「御」は古くは「み」と読み、神のものであることを示す接頭語でした。それが、天皇・宮中のものや、貴人のものであることを示す意味でも広く使用されるようになっていきました。
この「み」の上に、さらに尊敬の意を加えるために「大(オホ)」をつけ、「おほみ」と読むようになりました。そして「おほむ」「おほん」と音変化していきました。
その経緯で、「み」よりもむしろ「おほむ(おほん)」のほうが一般化し、あらゆるものへの敬意に広く用いられていきました。その一方で「み」のほうは、「神仏・天皇」に関わるものにほぼ限定されています。

「御門」「御幸」「御法」とかは、「天皇」に関わるものだもんね。

中世に近づくと、「おほむ(おほん)」は次第に「おん」と詰まっていきます。
中世以降に「おほん」と読むのは、古風な、あるいは大仰な言い方であるとされたようですね。
はて 名詞
「はて」は「果て」であり、「最後」「終わり」のことです。

「果ての年」は、「喪に服する期間の終わりの年」を意味する慣用表現です。訳としては「喪が明ける年」で大丈夫です。
ここでは「円融院」の「喪に服する期間」なので、「御」がついています。この「御」を訳に出すのは難しいのですが、「果て」についているわけですから、「お明けになる」などとしてしまってもいいですね。
この部分を「御一周忌」と訳している本もありました。喪の期間は、「天皇・父母・夫」が亡くなった場合は1年と規定されていますので、「円融院の御果ての年」を、「円融院の御一周忌」と訳すのは実情にあっていますね。
皆人 名詞
そのまま「皆人」と書いてもいいのですが、「人はみな」くらいに訳すのが一般的です。
直後の文脈から、「おほやけ」や「院の人」を指して「皆人」と言っていることがわかりますから、「宮中の人はみな」などとしてもよいですね。

女流文学の場合、周囲にいる「人」はほとんど「女房」ですから、「人」を「女房」と訳すことも多いです。
この場面についても、「女房」と訳している本もあります。
御服 名詞
「服」は、漢語の呉音読みで「ぶく」と読みます。

古文でもそのまま「ぶく」と言います。
なお、古文で「服」という場合には、基本的に「喪服」だと考えてください。

そう言えば現代語と違って、古文では普通の衣類のことを「服」って言ってる文にはめぐり合わないよね。
着る物のことは、「衣」って言ったり、「直衣」「狩衣」とか、衣類の名称で呼んだりするもんね。

よく、「喪に服す」なんて言いますけれど、古文で「服す(サ変動詞)」というと、それだけで「喪に服す」という意味を持ちます。
この文章での「服」は名詞なので、「喪服」と訳しましょう。
「御」の処理に迷いますが、訳出しにくいときは「御喪服」などとそのままつけておきましょう。選択肢問題の場合では、訳しにくい「御」は無視されていることもあります。