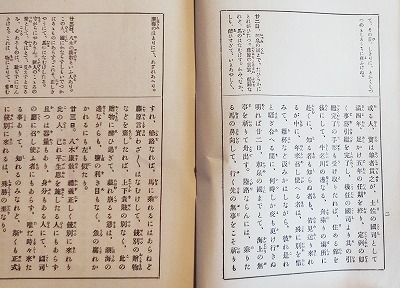『平家物語』より、「能登殿の最期(のとどののさいご)」の現代語訳です。

「能登殿」は「平教経」のことです。お父さんは「平教盛」(清盛の異母弟)です。
本文に登場する「新中納言」は「平知盛」のことです。お父さんは「平清盛」です。
「判官」は「源義経」のことです。義経は後白河法皇から、左衛門判官の任官を受けておりまして、ここでは「判官」と呼ばれています。「はんがん」と音読しますが、この義経の呼称にかんしては、「ほうがん」と読むのが一般的です。
およそ能登守教経の矢先にまはる者こそなかりけれ。
およそ能登守教経の矢先にまはる者こそなかりけれ。矢種のあるほど射尽くして、今日を最後とや思はれけん、赤地の錦の直垂に、唐綾縅の鎧着て、厳物作りの大太刀抜き、白柄の大長刀の鞘をはづし、左右に持つてなぎまはりたまふに、面を合はする者ぞなき。多くの者ども討たれにけり。
総じて能登守教経【平教経】の矢面に立ちまわる者はいなかった。手持ちの矢のあるかぎりを射尽くして、今日を最後とお思いになったのだろうか、赤地の錦の直垂に、唐綾縅の鎧を着て、厳物作り【いかめしく立派な作りの】大太刀を抜き、白木の柄の大長刀の鞘をはずし、左右の手に持って横に払ってまわりなさると、顔をあわせる者はいない。(源氏の)多くの者たちが討たれた。
新中納言、使者を立てて、~
新中納言、使者を立てて、「能登殿、いたう罪な作りたまひそ。さりとてよき敵か。」とのたまひければ、「さては大将軍に組めごさんなれ。」と心得て、打ち物茎短に取つて、源氏の船に乗り移り乗り移り、をめき叫んで攻め戦ふ。判官を見知りたまはねば、物具のよき武者をば判官かと目をかけて、馳せまはる。
新中納言【平知盛】は、(能登殿に)使者を立てて、「能登殿、あまり罪をお作りなさるな。そのようなことをして【そのように懸命に戦うのに】ふさわしい相手か、いや、そうではない。」とおっしゃったので、(能登殿は)「それでは大将軍【源義経】に組めというようだな。」と理解して、太刀や長刀の柄を短く持って、源氏の船に乗り移り乗り移り、大声で叫んで攻め戦う。(能登殿は)判官【義経】をご存知でいらっしゃらないので、武具の立派な武士を判官【義経】かと目をつけて、(舟から舟へ)駆けまわる。
判官も先に心得て、~
判官も先に心得て、表に立つやうにはしけれども、とかく違ひて、能登殿には組まれず。されどもいかがしたりけん、判官の舟に乗り当たつて、あはやと目をかけて飛んでかかるに、判官かなはじとや思はれけん、長刀脇にかい挟み、味方の舟の二丈ばかり退いたりけるに、ゆらりと飛び乗りたまひぬ。能登殿は、早業や劣られたりけん、やがて続いても飛びたまはず。
判官【義経】も(能登殿に狙われていることを)すでに理解して、正面に立つようにしたけれども、あれこれと行き違って、能登殿とはお組みにならない。しかしどうしたのであろうか、(能登殿の舟が)判官【義経】の舟に乗り当たって、やあっと目をつけて飛んでかかると、判官【義経】は(能登殿に)敵わないだろうとお思いになったのだろうか、長刀を脇に挟み、味方の舟で二丈【およそ6m】ほど離れていたものに、ゆらりと飛び乗りなさった。能登殿は、(このような)早業は(義経に)劣っていたのだろうか、すぐに続いてもお飛びにならない。
今はかうと思はれければ、~
今はかうと思はれければ、太刀・長刀海へ投げ入れ、甲も脱いで捨てられけり。鎧の草摺りかなぐり捨て、胴ばかり着て、大童になり、大手を広げて立たれたり。およそあたりを払つてぞ見えたりける。恐ろしなんどもおろかなり。能登殿、大音声をあげて、「われと思はん者どもは、寄つて教経に組んで生け捕りにせよ。鎌倉へ下つて、頼朝に会うて、ものひとこと言はんと思ふぞ。寄れや、寄れ。」とのたまへども、寄る者一人もなかりけり。
(能登殿は)もうこれまでとお思いになったので、太刀・長刀を海へ投げ入れ、甲も脱いでお捨てになった。鎧の草摺りを荒々しく引きちぎって、胴だけを着て、ざんばら髪【激しい戦いによって髪の結びがほどけ、童のようになった髪型】になり、大手を広げてお立ちになった。(その姿は)総じて周り(の者)を寄せつけないように見えていた。恐ろしいなどという言葉では言い尽くせない。能登殿は、大声をあげて、「我こそはと思うような者は、近寄って教経【私】と組んで生け捕りにせよ。鎌倉に下って、頼朝に会って、何か一言言おうと思うぞ。寄ってこい、寄ってこい。」とおっしゃるが、近寄る者は一人もいなかった。
ここに、土佐国の住人、~
ここに、土佐国の住人、安芸郷を知行しける安芸大領実康が子に、安芸太郎実光とて、三十人が力持つたる大力の剛の者あり。我にちつとも劣らぬ郎等一人、弟の次郎も普通には優れたるしたたか者なり。安芸太郎、能登殿を見奉つて申しけるは、「いかに猛うましますとも、われら三人取りついたらんに、たとひたけ十丈の鬼なりとも、などか従へざるべき。」とて、主従三人小舟に乗つて、能登殿の舟に押し並べ、「えい。」と言ひて乗り移り、甲の錣を傾け、太刀を抜いて、一面に打つてかかる。
ここに、土佐国の住人で、安芸郷を支配した安芸大領実康の子に、安芸太郎実光といって、三十人ぶんの力を持っている怪力の武勇にすぐれた者がいる。自分に少しも劣らない家来が一人(いて)、(また)弟の次郎も普通よりは優れている気丈な者である。安芸太郎が、能登殿を見申し上げて申し上げたことには、「どれほど勇猛でいらっしゃっても、我ら三人が組み付いたとしたら、例え背丈が十丈【およそ30m】の鬼であっても、どうして従えられないだろうか、いや従えられるはずだ。」といって、主従三人が小舟に乗って、能登殿の舟に押し並べ、「えい。」と言って乗り移り、兜の錣【首の後ろを守るところ】を傾けて、太刀を抜いて、いっせいに討ってかかる。
能登殿のちつとも騒ぎたまはず、~
能登殿のちつとも騒ぎたまはず、まつ先に進んだる安芸太郎が郎等を、裾を合はせて、海へどうど蹴入れたまふ。続いて寄る安芸太郎を、弓手の脇に取つてはさみ、弟の次郎をば馬手の脇にかいばさみ、ひと締め締めて、「いざ、うれ、さらばおのれら、死出の山の供せよ。」とて、生年二十六にて、海へつつとぞ入りたまふ。
能登殿は少しもお騒ぎにならず、真っ先に進んだ安芸太郎の家来を、裾と裾がふれあうほど引き寄せて、海にどっと蹴り入れなさる。続いて近寄る安芸太郎を、弓手【左手】の脇に取って挟み、弟の次郎を馬手【右手】の脇に挟み、ひと締め締め上げて、「さあ、お前、それではお前ら、死出の山の供をせよ。」と言って、生年二十六で、海へさっとお入りになる。
新中納言、~
新中納言、「見るべきほどのことは見つ。今は自害せん。」とて、乳母子の伊賀平内左衛門家長を召して、「いかに、約束は違ふまじきか。」とのたまへば、「子細にや及び候ふ。」と中納言に鎧二領着せ奉り、我が身も鎧二領着て、手を取り組んで海へぞ入りにける。これを見て、侍ども二十余人、後れ奉らじと、手に手を取り組んで、一所に沈みけり。その中に、越中次郎兵衛・上総五郎兵衛・悪七兵衛・飛騨四郎兵衛は、何としてか逃れたりけん、そこをもまた落ちにけり。
新中納言【平知盛】は、「見なければならないことは見た。今は自害しよう。」といって、乳母子の伊賀平内左衛門家長をお呼びになって、「どうであるか、(同じところで死ぬという)約束は違えないだろうか。」とおっしゃると、(家長は)「こまごまと申すに及びましょうか、いや、(何も申すことは)ありません。」と、中納言に鎧を二領着せ申し上げ、自分も鎧を二領着て、手を取り組んで海へ入った。これを見て、(平家の)侍たち二十人余りが、遅れ申し上げまいと、手を取り組んで、同じ場所に沈んだ。その中に、越中次郎兵衛・上総五郎兵衛・悪七兵衛・飛騨四郎兵衛は、どのようにして逃れたのだろうか、そこをもまた落ちのびた。
海上には赤旗・赤印投げ捨て、~
海上には赤旗・赤印投げ捨て、かなぐり捨てたりければ、竜田川のもみぢ葉を嵐の吹き散らしたるがごとし。汀に寄する白波も、薄紅にぞなりにける。主もなきむなしき舟は、潮にひかれ、風に従って、いづくをさすともなく揺られゆくこそ悲しけれ。
海上には(平家の)赤旗・赤印が投げ捨て(てあり)、荒々しく捨ててあったので、竜田川の紅葉の葉を嵐が吹き散らしているようだ。水際にうち寄せる白波も、(斬られた者たちの血で)薄紅色になっていた。(乗るはずの)主人もいない空虚な舟は、潮に引かれ、風に従って、どこを目指すこともなく揺られていくことが悲しい。