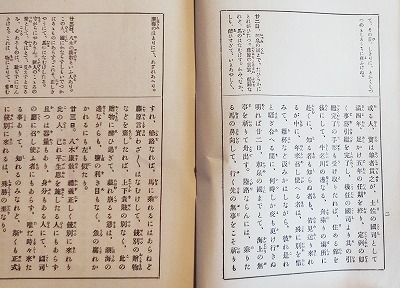『蜻蛉日記』より、「なげきつつひとり寝る夜/うつろひたる菊」の現代語訳です。
テキストによっては、「町の小路の女」などのタイトルです。
九月ばかりになりて、~
さて、九月ばかりになりて、出でにたるほどに、箱のあるを手まさぐりに開けて見れば、人のもとにやらむとしける文あり。あさましさに、見てけりとだに知られむと思ひて、書きつく。
さて、九月ごろになって、(兼家が)出ていった【帰ってしまった】時に、文箱があるのを何気なく開けて見ると、(他の)人のところに送ろうとした手紙がある。驚きあきれて、(手紙を)見たということだけでも知ってもらおうと思って、(歌を)書きつける。
うたがはし ~
うたがはし ほかに渡せる ふみ見れば ここやとだえに ならむとすらむ
など思ふほどに、むべなう、十月つごもりがたに、三夜しきりて見えぬ時あり。つれなうて、「しばしこころみるほどに。」など、気色あり。
疑わしい。他(の女)に送ろうとする手紙を見ると、ここ【私のところ】に来るのは途絶えようとしているのだろうか。
などと思ううちに、案の定、十月の末ごろに、三晩続いて姿を見せない時がある。(しかし兼家は)平然として、「(あなたの気持ちを)しばらく試しているうちに(三日が経った)。」などと、あやしげである【思わせぶりなことを言う】。
これより、~
これより、夕さりつかた、「内の方ふたがりけり。」とて出づるに、心得で、人をつけて見すれば、「町の小路なるそこそこになむ、とまり給ひぬる。」とて来たり。さればよと、いみじう心憂しと思へども、いはむやうも知らであるほどに、二、三日ばかりありて、暁がたに門をたたく時あり。
ここ【私の家】から、夕方、「宮中の方が悪い方角にあたっていた【(陰陽道の)方塞がりだった】(そのため、いったん場所を変えよう)。」と言って出かけるので、(私は)納得できず、(召使いの)人を後につけて見させると、「町の小路にあるどこそこに、(兼家の車が)お止まりになった。」と言って(戻って)来た。やっぱりだと、たいそうつらいと思うけれど、(その気持ちを)言おうとする方法もわからずにいるうちに、二、三日ほどたって、夜明けごろに門をたたく(音がする)時がある。

「内の方ふたがりけり」は、「宮中から(こちら)の方角が悪い方角にあたっていた(だからここにいるわけにいかなかった)」と考えることもできます。
ここでの「ふさがる」は、陰陽道で「禁忌の方角にあたっている」ということです。名詞を用いて「方塞がりである」と訳してもOKです。
行こうとする方角に天一神(中神)がいて、そのまま行くと災難に遭うとされています。その状態で目的地に向かう場合には、「方違へ(かたたがへ)」をします。いったん別の場所に行って宿泊してから、角度を変えて再び出発するのです。
さなめりと思ふに、~
さなめりと思ふに、憂くて、開けさせねば、例の家とおぼしきところにものしたり。つとめて、なほもあらじと思ひて、
嘆きつつ ひとり寝る夜の あくる間は いかに久しき ものとかは知る
と、例よりはひきつくろひて書きて、移ろひたる菊にさしたり。
そのようだ(兼家が来た)と思うと、つらくて、開けさせないでいると、例の家【小路の女の家】と思われる所に行ってしまった。翌朝、やはりこのままではいられないと思って、
嘆きながら、ひとりで寝る夜が明けるまでの間は、どんなに長いものとおわかりか、いや、おわかりにはなるまい。
と、いつもよりは体裁を整えて書いて、色あせている菊に挿した(そしてその文を送った)。
返り言、~
返り言、「あくるまでもこころみむとしつれど、とみなる召使の来あひたりつればなむ。いと理なりつるは。
げにやげに 冬の夜ならぬ 真木の戸も おそくあくるは わびしかりけり」
(兼家の)返事は、「夜が開けるまでためしに待とうとしたが、急な(用事をもつ)召し使いが来合わせたので(引き返した)。(あなたが怒るのも)本当にもっともなことだ。
ほんとうにまったく(そのとおりだ。とはいえ、)冬の夜ではない(今夜ここで)真木の戸がなかなか開かないことも、つらいものだなあ。」

「わかるわかるよ本当にそうだよねえ。さて、あなたがつらいと言っていた冬の夜ではないにしても、目の前の戸がさっさと開かないのも自分にとってはつらいよねえ」
と言っているのですね。

兼家はげにげに言ってるだけで道綱母の気持ちを何もわかってない歌だよね。
さても、~
さても、いとあやしかりつるほどに、事なしびたり。しばしは忍びたるさまに、「内に。」など言ひつつぞあるべきを、いとどしう心づきなく思ふことぞ限りなきや。
それにしても、たいそう不思議であるほど、そしらぬふりをしている。(普通だったら)しばらくは人目を避けている様子で、「宮中に(参上する)。」などと言いながら通うのが当然であるのに(言い訳すらしない)、ますます不愉快に思うことはこの上ないことよ。

『大鏡』にも、このお話をもとにしたところがあります。