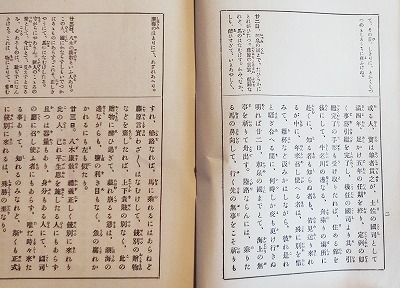かくいふほどに、~
かくいふほどに、秋にもなりぬ。住吉には、月日の積もりゆくままに、いとどあはれさもまさり、「いかになるべき身にか」とおぼし嘆く。尼君もうち泣きて、「わらはは残り少なき身に侍る。めでたうあたらしき御ありさまを、かかるあさましき柴の庵の内に押し籠め奉りて、はかなくなり侍りなば、いかにならせ給ふべき御ありさまに」と言ひつづけて泣けば、姫君うち泣きて、「世にあり経んと思ふ身ならばこそ」とて、泣きつつ過ごし給ふ。
このように言ううちに、秋にもなった。住吉では、月日が経っていくうちに、ますます悲しみも増え、「どうなるはずの身の上であるのか」とお思いになり嘆く。尼君も泣いて、「私は(人生の)残りが少ない身でございます。すばらしくもったいない(姫君の)お姿を、このような粗末な柴の庵の中に押しこめ申し上げて、(私が)死んでしまいましたなら、どのようにおなりになる御身の上であるか」と言い続けて泣くと、姫君は泣いて、「この世に生き続けようと思う身であるならばともかく(そうではない)」と言って、泣きながらお過ごしになる。
中将は長月のころ、~
中将は長月のころ、長谷寺に詣で給ひて、七日籠もりて、また異ごとなく祈り申させ給ひけり。七日といふ夜もすがら行ひ明かして、暁方に少しまどろみ給ふに、やんごとなき女房の、うちそばみてゐ給へるを見給へば、わが思ふ人なり。うれしく、「かく悲しきことを思はせ給ふらん。いかばかり嘆くとか知らせ給ふ」とて恨み給へば、姫君、「かくまでおぼしめすとは知り侍らず。御心ざしのありさま、ありがたく見侍れば、参りつるなり。今は帰りなん」とて立ち給ふを、「いかに、おはしどころを知らせさせ給へ」とて、袖をひかへ給へば、
わたつ海のそことも知らずわびぬればすみよしとこそ海人は言ふなれ
とながめ給ふと聞き、御返事するとおぼして、うちおどろき給ひぬ。「夢と知りせば」と思ふに、悲しさ言ふはかりなし。「ひとへに仏の御教へなり。住吉を尋ねん」とおぼして、明けぬれば出で給ふ。
中将は九月ころ、長谷寺にお参りになって、七日間籠って、また他のことはなく(姫君の居場所を知る以外のことはなく)お祈り申し上げなさった。七日という日数、一晩中勤行して夜を明かして、暁のころ少しまどろみなさると、高貴な女房が、横を向いて座っていらっしゃるのを(中将が)見なさると、自分の思う人【姫君】である。(中将は)うれしく、「(どうして)このように悲しいことを思わせなさるのだろう。どれほど(私が)嘆くとおわかりになるか」と言ってお恨みになると、姫君は、「これほど(私のことを)お思いになるとはわかっていません。お心のありさま、めったにないと思いますので、参上したのである。今はもう帰ろう」と言ってお立ちになるのを、「もしもし、いらっしゃるところをお知らせください」と言って、(姫君の)袖をお取りになると、
海の底ともわからずに嘆いていたところ、住むのによい「住吉」と海人は言うようだ。
と歌を口ずさむと(中将は)聞いて、お返事をするとお思いになって、(そこで)目をお覚ましになった。「夢と知っていたならば(目を覚まさなかったのに)」と思うと、悲しさは言いようがない。「ひとえに仏のお教えである。住吉を訪ねよう」とお思いになって、夜が明けたところで出発なさる。
山城の泉川より、~
山城の泉川より、御供の人を帰して、むつましくおぼしめさるる随身、舎人童なるを具して行き給ふ。御供には人あまたあれども、帰すなり。「精進ついでに、住吉、天王寺へと思ふなり。このよしを申されよ」とのたまへば、「さらに候ふまじきことなり。京よりこそ参り給はめ。さらずは、みな御供にこそ参り侍らん」と申せば、「いかにかやうには申すぞ。深く思ふやうあり。とくとく帰れ」と、あながちにのたまへば、おのおの帰りぬ。
山城の泉川から、お供の人を帰して、親しくお思いになっている随身、舎人童である者を連れてお行きになる。お供にはたくさんいるけれども、帰すのである。「精進のついでに、住吉、天王寺へ(参ろう)と思うのである。このいきさつを(私の親に)申し上げよ」と(中将が)おっしゃると、「決してあってはならないことでございます。(いったん戻って)京からお参りください。そうでなければ、みな(このまま住吉・天王寺まで)お供に参りましょう」と申し上げると、「どうしてそのように申し上げるのか。(私は)深く思うことがある。早く早く帰れ」と、強引におっしゃると、(お供の者たちは)それぞれ帰った。