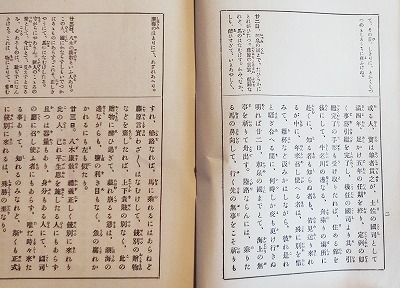『堤中納言物語』より、「虫愛づる姫君(むしめづるひめぎみ)」の現代語訳(前半)です。
蝶てふめづる姫君の住みたまふかたはらに、~
蝶めづる姫君の住みたまふかたはらに、按察使の大納言の御むすめ、心にくくなべてならぬさまに、親たちかしづきたまふこと限りなし。
蝶をかわいがる姫君が住んでいらっしゃる(屋敷の)隣に、按察使の大納言の姫君が(いらっしゃり、その姫君の)奥ゆかしく並々でない様子に、親たちが大切にお育てになることはこの上ない。

「按察使(あぜち)」というのは、令外の官のひとつで、国司の仕事や、各国の人々の様子などを視察する役職です。平安時代には陸奥と出羽だけが任地となり、主に大納言や中納言が兼務しました。
この姫君ののたまふこと、~
この姫君ののたまふこと、「人々の、花、蝶やとめづるこそ、はかなくあやしけれ。人は、まことあり、本地たづねたるこそ、心ばへをかしけれ」とて、よろづの虫の、恐ろしげなるを取り集めて、「これが、成らむさまを見む」とて、さまざまなる籠箱どもに入れさせたまふ。中にも「烏毛虫の、心深きさましたるこそ心にくけれ」とて、明け暮れは、耳はさみをして、手のうらにそへふせて、まぼりたまふ。
この姫君がおっしゃることには、「人々が、花よ蝶よとかわいがるのは、浅はかでおかしなことだ。人は、誠実な心があり、ものの本質を追究することこそ、心がまえが立派なのだ」と言って、いろいろな虫で、恐ろしそうなものを採集して、「これが、成長する様子を見よう」と言って、さまざまな虫籠などに(虫を)入れさせなさる。中でも、「毛虫が、思慮深い様子をしているのは奥ゆかしい」と言って、明けても暮れても、(額から頬に垂らした)髪を耳の後ろにかきあげて、(毛虫を)手のひらに添えて這わせて、じっと見守りなさる。
若き人々は、~
若き人々は、おぢ惑ひければ、男の童の、ものおぢせず、いふかひなきを召し寄せて、箱の虫どもを取らせ、名を問ひ聞き、いま新しきには名をつけて、興じ給ふ。
若い女房たちは、恐れうろたえたので、男の童で、物おじしない、身分の低い者を呼び寄せて、箱の虫たちを取らせ、名を問い尋ね、さらに新種の虫には名をつけて、おもしろがっていらっしゃる。
「人はすべて、~
「人はすべて、つくろふところあるはわろし」とて、眉さらに抜きたまはず。歯黒め、「さらにうるさし、きたなし」とて、つけたまはず、いと白らかに笑みつつ、この虫どもを、朝夕べに愛したまふ。
「人は総じて、取り繕うところがあるのはよくない」といって、眉毛は全くお抜きにならない。お歯黒も、「まったく煩わしい、不潔だ」と言って、おつけにならず、たいそう白い歯で笑いながら、この虫たちを、朝に夕にかわいがりなさる。
人々おぢわびて逃ぐれば、~
人々おぢわびて逃ぐれば、その御方は、いとあやしくなむののしりける。かくおづる人をば、「けしからず、ばうぞくなり」とて、いと眉黒にてなむ睨みたまひけるに、いとど心地なむ惑ひける。
女房たちが恐れ嘆いて逃げると、その姫君のお部屋は、たいそう甚だしく大騒ぎをした。このように怖がる女房を、「異様だ、無作法だ」と言って、たいそう黒々とした眉で睨みなさったので、(女房たちは)いっそう気持ちが乱れた。
親たちは、~
親たちは、「いとあやしく、さまことにおはするこそ」と思しけれど、「思し取りたることぞあらむや。あやしきことぞ。思ひて聞こゆることは、深く、さ、いらへたまへば、いとぞかしこきや」と、これをも、いと恥づかしと思したり。
親たちは、「とてもおかしく、風変わりでいらっしゃる」とお思いになったが、「お悟りになっていることがあるのだろうか。不思議なことだ。(私たちが姫のために)思って申し上げることには、深く、そのように【悟ったように】お答えなさるので、たいそう恐れ入ったことよ」と、これ【姫君の言動】をも、(世間に対して)たいそうきまりが悪いとお思いになった。
「さはありとも、~
「さはありとも、音聞きあやしや。人は、みめをかしきことをこそ好むなれ。むくつけげなる烏毛虫を興ずなると、世の人の聞かむも、いとあやし」と、聞こえたまへば、「苦しからず。よろづのことどもをたづねて、末を見ればこそ、事はゆゑあれ。いとをさなきことなり。烏毛虫の、蝶とはなるなり」そのさまのなり出づるを、取り出でて見せたまへり。
「そうであっても、外聞が悪いよ。人は、見た目の美しいことを好むのである。気味の悪い毛虫をおもしろがっているそうだと、世間の人が聞くとしたら、たいそう不都合だ」と、申し上げなさると、(姫君は)「かまわない。万事のことを探究して、行く末を見るからこそ、物事はわけがわかる。(見た目にこだわるのは)たいそう幼稚なことである。毛虫が、蝶となるのだ」(と、)毛虫が蝶に変化するところを、(このとおりと)取り出してお見せになった。
「きぬとて、~
「きぬとて、人々の着るも、蚕のまだ羽つかぬにし出だし、蝶になりぬれば、いともそでにて、あだになりぬるをや」とのたまふに、言ひ返すべうもあらず、あさまし。
「絹といって、人々が着るものも、蚕がまだ羽のつかないころに作り出して、蝶になってしまうと、全く相手にせず、役に立たないものなってしまうのだよ」とおっしゃるので、(親たちは)言い返すこともできず、あきれている。
さすがに、~
さすがに、親たちにもさし向かひたまはず、「鬼と女とは、人に見えぬぞよき」と案じたまへり。母屋の簾を少し巻きあげて、几帳いでたて、しかくさかしく言ひ出だしたまふなりけり。
そうはいってもやはり、(姫君は)親たちにも面と向かって言うことはなさらず、「鬼と女は、人に見られないのがよい」とあれこれ考えなさっている。母屋の簾を少し巻き上げて、几帳を押し立てて、このように利口そうに理屈を並べなさるのであった。
これを、~
これを、若き人々聞きて、「いみじくさかしたまへど、いと心地こそ惑へ、この御遊びものは」「いかなる人、蝶めづる姫君につかまつらむ」とて、兵衛といふ人、
いかでわれ とかむかたふなく いてしがな 烏毛虫ながら 見るわざはせじ
と言へば、
これを、若い女房たちが聞いて、「並々でなくもてはやしなさるけれど、たいそう気持ちが乱れる、このお遊びには」「どのような人が、蝶をかわいがる姫君にお仕えしているのだろう(そちらがうらやましい)」と言って、兵衛という女房が、
――どうにかして、姫君に道理を説くことなく、(この屋敷に)いたいものだ。(姫君もいつまでも)毛虫のままでいることはないだろう【いずれは蝶になるだろう】。
と言うと、
小大輔といふ人、~
小大輔といふ人、笑ひて、
うらやまし 花や蝶やと 言ふめれど 烏毛虫くさき よをも見るかな
など言ひて笑へば、
小大輔という女房が、笑って、
――うらやましいことだ。(人は)花や蝶やと言うようだが、(私たちは)毛虫くさい中で、毎日を過ごしているのだな。
などと言って笑うと、
「からしや、~
「からしや、眉はしも、烏毛虫だちためり」「さて、歯ぐきは、皮のむけたるにやあらむ」とて、左近といふ人、
「冬くれば 衣たのもし 寒くとも 烏毛虫多く 見ゆるあたりは
衣など着ずともあらなむかし」など言ひあへるを、
(女房たちは、)「つらいわ、眉のところも、毛虫のようであろう」「そうして、歯ぐきは、(毛虫の)皮のむけたものであろう」と言って、左近という女房が、
――「冬が来ると、着物は(十分あると)頼りになる。寒くても、毛虫がたくさんいるこの屋敷では。
着物など着なくても(そのまま)いてほしいよ」などと言い合っているのを、
とがとがしき女聞きて、~
とがとがしき女聞きて、「若人たちは、何事言ひおはさうずるぞ。蝶めでたまふなる人も、もはら、めでたうもおぼえず。けしからずこそおぼゆれ。さてまた、烏毛虫ならべ、蝶といふ人ありなむやは。ただ、それが蛻くるぞかし。そのほどをたづねてしたまふぞかし。それこそ心深けれ。蝶はとらふれば、手にきりつきひて、いとむつかしきものぞかし。また、蝶はとらふれば、瘡病せさすなり。あなゆゆしとも、ゆゆし」と言ふに、いとど憎さまさりて、言ひあへり。
口うるさい女房が聞いて、「若い女房たちは、何を言っていらっしゃるのだ。蝶をかわいがっていらっしゃる(隣の)人も、けっして、すばらしいとは思わない。異様だと思う。そうしてまた、毛虫を並べて、蝶という人がいるだろうか、いや、いない。ただ、それ【毛虫】が脱皮するのだよ。(姫君は)その過程を探究していらっしゃるのだよ。それこそ深い心構えだ。蝶は捕らえると、手に粉がついて、たいへん気持ち悪いものだよ。また、蝶は捕らえると、わらわやみ【マラリアのような熱病】を起こさせるという。ああひどい、ひどい」と言うと、(若い女房たちは)ますます憎らしくなって、(悪口を)言い合った。
この虫どもとらふる童べには、~
この虫どもとらふる童べには、をかしきもの、かれが欲しがるものを賜へば、さまざまに、恐ろしげなる虫どもを取り集めて奉る。「烏毛虫は、毛などはをかしげなれど、おぼえねば、さうざうし」とて、蟷螂、蝸牛などを取り集めて、歌ひののしらせて聞かせたまひて、われも声をうちあげて、「かたつぶりのお、つのの、あらそふや、なぞ」といふことを、うち誦じたまふ。
この虫どもを捕らえる童には、(姫君が)興味深いもの、童が欲しがるものをくださるので、(童たちは)いろいろと、恐ろしそうな虫たちを採集して(姫君に)差し上げる。「毛虫は、毛などはおもしろいが、(故事などを連想させるものとは)思えないので、物足りない」といって、かまきり、かたつむりなどを取り集めて、大声で歌って申し上げなさって、姫君も声を張り上げて、「かたつむりの、角の、争うのは、何だ」ということを詠唱なさる。

白居易の詩歌に、次のものがあります。
*********************
蝸牛角上争何事
石火光中寄此身
随富随貧且歓楽
不開口笑是癡人
蝸牛角上何事をか争ふ
石火光中此の身を寄す
富に随ひ貧に随ひ且らく歓楽せよ
口を開いて笑はざるは是れ癡人
かたつむりの角の上(のようなせまい場所)で、(人は)何を争っているのか。
(人生は)火打ち石の火花のような瞬間に、身を寄せているのだ。
(だから)貧富それぞれに応じて、その間、歓び楽しむのがよい。
口を開いて笑うこともないのは、おろかな人である。
*********************
「童」と「姫君」は、こういった詩をベースにして、虫を取り集めて遊んでいるのですね。

わ、童も教養があるんだな!
童べの名は、~
童べの名は、例のやうなるはわびしとて、虫の名をなむつけたまひたりける。けらを、ひきまろ、いなかたち、いなごまろ、あまびこなんどつけて、召し使ひたまひける。
童の名は、一般的なものはつまらないと言って、虫の名をおつけになった。「けらを」ひきまろ」「いなかたち」「いなごまろ」「あまびこ」などとつけて、召し使っていらっしゃった。

けらを ⇒ おけら
ひきまろ ⇒ ひきがえる
いなごまろ ⇒ いなご(しょうりょうばった)
あまびこ ⇒ やすで
のことだと言われています。
「いなかたち」は不詳です。

お話のつづきはこちら。