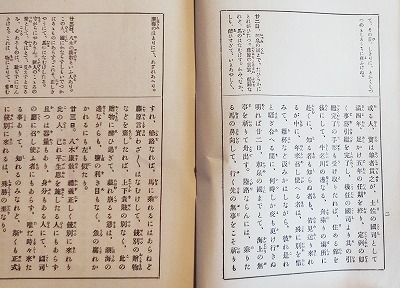『平家物語』より、「忠度の都落ち(ただのりのみやこおち)」の現代語訳です。

「忠度」は「平忠度」です。「清盛」の異母弟であり、お父さんは「忠盛」です。
本文に出てくる「俊成」は、『千載和歌集』の撰者である「藤原俊成」のことです。「藤原定家」のお父さんで、平安時代におけるトップクラスの歌人です。
「平忠度」は、この「俊成」に師事しておりまして、和歌の腕前も相当なものでした。
薩摩守忠度は、~
薩摩守忠度は、いづくよりや帰られたりけん、侍五騎、童一人、わが身ともに七騎取つて返し、五条の三位俊成卿の宿所におはして見給へば、門戸を閉ぢて開かず。「忠度。」と名のり給へば、「落人帰り来たり。」とて、その内騒ぎ合へり。
薩摩守忠度は、(都落ちしたのち)どこから(都に)お帰りになったのだろうか、侍五騎、童一人、自分と合わせて七騎で引き返し、五条三位俊成卿の屋敷にいらっしゃってご覧になると、門を閉じて開かない。「忠度。」と名乗りなさると、「落人が帰って来た。」と言って、門の中では騒ぎ合っている。
薩摩守馬より下り、~
薩摩守馬より下り、みづから高らかにのたまひけるは、「別の子細候はず。三位殿に申すべきことあつて、忠度が帰り参つて候ふ。門を開かれずとも、この際まで立ち寄らせ給へ。」とのたまへば、俊成卿、「さることあるらん。その人ならば苦しかるまじ。入れ申せ。」とて、門を開けて対面あり。ことの体、何となうあはれなり。
薩摩守は馬から下り、自分自身で大声でおっしゃったことは、「特別のわけはございません。三位殿に申し上げたいことがあって、忠度が帰って参ってございます。門をお聞きにならなくとも、この【門の】そばまでお寄りになってください。」とおっしゃるので、俊成卿は、「そのようなこと【帰って来るほどのわけ】があるのだろう。その人ならば差し支えあるまい。お入れ申し上げよ。」と言って、門を開けて対面になる。ことの様子【対面する様子】は、すべてにわたってしみじみと趣き深い。
薩摩守のたまひけるは、~
薩摩守のたまひけるは、「年ごろ申し承つてのち、おろかならぬ御事に思ひ参らせ候へども、この二、三年は京都の騒ぎ、国々の乱れ、しかしながら当家の身の上のことに候ふ間、疎略を存ぜずといへども、常に参り寄ることも候はず。君すでに都を出でさせ給ひぬ。一門の運命はや尽き候ひぬ。撰集のあるべき由承り候ひしかば、生涯の面目に、一首なりとも、御恩をかうぶらうど存じて候ひしに、やがて世の乱れ出できて、その沙汰なく候ふ条、ただ一身の嘆きと存ずる候ふ。
薩摩守がおっしゃるには、「長年の間(歌を)教えていただいてのち、(俊成のことを)いい加減でないことと思い申しあげましたが【いい加減に思い申し上げることはございませんが】、この二、三年は、京都の騒ぎや、国々の乱れ、そっくりそのまま全て当家【平家】の身の上のことにございますので、(俊成のことを)ないがしろには思っておりませんといっても、いつもお近くに参上することもありませんでした。君【安徳天皇】はすでに都をお出になられた。(平家の)一門の運命はすでに尽きました。勅撰和歌集の編集があるだろうということをうかがいましたので、(私の)生涯の名誉のために、一首であっても、ご恩を受けよう【自作を撰集に入れてもらおう】と存じておりましたが、そのまますぐに世の乱れ【源平の争い】が起こって、その(撰集の)命令がなくなっておりますことは、まったく(私の)一身の嘆きと存じております。
世静まり候ひなば、~
世静まり候ひなば、勅撰の御沙汰候はんずらむ。これに候ふ巻き物のうちに、さりぬべきもの候はば、一首なりとも御恩をかうぶつて、草の陰にてもうれしと存じ候はば、遠き御守りでこそ候はんずれ。」とて、日ごろ詠みおかれたる歌どもの中に、秀歌とおぼしきを百余首書き集められたる巻き物を、今はとてうつ立たれけるとき、これを取つて持たれたりしが、鎧の引き合はせより取り出でて、俊成卿に奉る。
世の中が静まりましたならば、勅撰のご命令がございましょう。ここにございます巻き物の中に、(勅撰集に載せるのに)ふさわしいものがございますならば、一首であってもご恩を受けて【載せてもらって】、草の陰でも【私が死んだのちでも】うれしいと存じますならば、遠い(あの世からの)お守りでございましょう【遠いあの世からあなたをお守りいたしましょう】。」と言って、普段から詠みおかれている歌たちの中で、秀歌と思われる歌を百首あまり書き集められた巻き物を、今は【もうこれまで】と思って(都を)出発なさった時、これを取ってお待ちなっていたが、(それを)鎧の引き合わせから取り出して、俊成卿に差し上げる。
三位これを開けて見て、~
三位これを開けて見て、「かかる忘れ形見を給はりおき候ひぬる上は、ゆめゆめ疎略を存ずまじう候ふ。御疑ひあるべからず。さてもただ今の御渡りこそ、情けもすぐれて深う、あはれもことに思ひ知られて、感涙おさへがたう候へ。」とのたまへば、薩摩守喜んで、「今は西海の波の底に沈まば沈め、山野にかばねをさらさばさらせ。浮き世に思ひおくこと候はず。さらばいとま申して。」とて、馬にうち乗り、甲の緒を締め、西をさいてぞ歩ませ給ふ。
三位【俊成】はこれ【巻き物】を開けて見て、「このような忘れ形見をいただきましたうえは、決してぞんざいに扱いますまい。お疑いにならなくてよい。それにしてもただ今のお出で【ご訪問】は、風流心もすぐれて深く、しみじみとした情趣も特別に感じられて、感涙を抑えがたくございます。」とおっしゃると、薩摩守【忠度】は喜んで、「今は西海の波の底に沈むのなら沈んでもよい、山野にしかばねをさらすのならさらしてもよい。このつらい世に思い残すことはございません。それではお別れを申し上げて。」と言って、馬に乗り、甲の緒を締め、西を指して【西に向かって】(馬を)歩ませなさる。
三位後ろをはるかい見送つて立たせたれば、~
三位後ろをはるかに見送つて立たれたれば、忠度の声とおぼしくて、「前途ほど遠し、思ひを雁山の夕べの雲に馳す。」と、高らかに口ずさみ給へば、俊成卿、いとど名残惜しうおぼえて、涙をおさへてぞ入り給ふ。
三位は(忠度の)後姿を遠くになるまで見送ってお立ちになっていると、忠度の声と思われて、「前途ほど遠し、思ひを雁山の夕べの雲に馳す【これから先の旅路は遠い、途中で越える雁山の夕べの雲に思いを馳せる】。」と、高らかに口ずさみなさるので、俊成卿は、いっそう名残惜しく思われて、涙を抑えて(門の内側に)お入りになる。
そののち、世静まつて、~
そののち、世静まつて、千載集を撰ぜられけるに、忠度のありしありさま、言ひおきし言の葉、今さら思ひ出でてあはれなりければ、かの巻き物のうちに、さりぬべき歌いくらもありけれども、勅勘の人なれば、名字をばあらはされず、「故郷の花」といふ題にて詠まれたりける歌一首ぞ、「よみ人知らず」と入れられける。
さざなみや 志賀の都は あれにしを 昔ながらの 山桜かな
その身、朝敵となりにし上は、子細に及ばずと言ひながら、うらめしかりしことどもなり。
その後、(戦乱が終わり)世が静まって、(俊成が)千載集をお選びになった時に、忠度の生前の有様や、言い残した言葉を、今一度思い出してしみじみと感慨深いので、あの(忠度の)巻き物の中に、ふさわしい歌はたくさんあったけれども、(忠度は)天皇のおとがめを受けた人であるので、姓名を公にされず、「故郷の花」という題でお詠みになった歌一首を、「よみ人しらず【作者不明】」としてお入れになった。
志賀の旧都は荒れ果ててしまったが、長等山の山桜は昔のままだなあ。
その身【忠度の身】が、朝敵となってしまったうえは、あれこれ言うに及ばないとは言うものの、残念なことである。