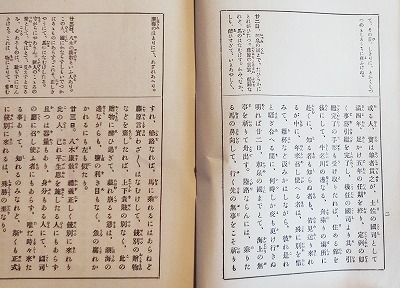『徒然草』より、「花は盛りに(はなはさかりに)」の現代語訳です。
花は盛りに、~
花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは。雨に対ひて月を恋ひ、垂れこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情け深し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見どころ多けれ。
(桜の)花はその盛りに【満開のときに】、月は雲りのないものだけを見るものだろうか、いや、そうではない。雨に向かって(見えない)月を恋い慕い、すだれを降ろして(家の中に)引きこもって、春の移り変わりを知らない(でいる)のも、やはりしみじみとして趣深い。今にも咲きそうなほどの梢、(花が)散り、しおれている(花が点在している)庭などにこそ見る価値が多い。
歌の詞書にも、~
歌の詞書にも、「花見にまかれりけるに、早く散り過ぎにければ」とも、「障ることありてまからで」なども書けるは、「花を見て」と言へるに劣れることかは。花の散り、月の傾くを慕ふ習ひはさることなれど、ことにかたくななる人ぞ、「この枝、かの枝散りにけり。今は見どころなし。」などは言ふめる。
歌の詞書にも、「花見に参ったがが、もうすでに散り果ててしまったので」とも、「都合の悪いことがあって(花見に)参らずに・・・」などと書いてあるものは、「花を見て・・・」と言っているのに劣っているか、いや劣っていない。花が散り、月が(西に)傾くのを恋い慕うならわしはもっともなことであるが、とくに情趣を解さない人は、「この枝も、あの枝も散ってしまった。今は見る価値がない。」などと言うようだ。
よろづのことも、~
よろづのことも、初め終はりこそをかしけれ。男女の情けも、ひとへに逢ひ見るをばいふものかは。逢はでやみにし憂さを思ひ、あだなる契りをかこち、長き夜をひとり明かし、遠き雲居を思ひやり、浅茅が宿に昔をしのぶこそ、色好むとは言はめ。
何事も、最初と最後こそ趣深い。男女の情愛も、ひたすらに逢い、契りを結ぶことをいうものか、いやそうではない。逢わずに終わってしまったつらさを思い、はかない約束を嘆き、長い夜を一人で明かして、遠く離れた住まいを思いやり、(チガヤの茂る)荒れ果てた住まいで昔を懐かしむことこそ、恋愛の情趣を味わうことだと言うのだろう。
望月の隈なきを千里の外まで眺めたるよりも、~
望月の隈なきを千里の外まで眺めたるよりも、暁近くなりて待ち出でたるが、いと心深う、青みたるやうにて、深き山の杉の梢に見えたる、木の間の影、うちしぐれたる群雲隠れのほど、またなくあはれなり。椎柴・白樫などの濡れたるやうなる葉の上にきらめきたるこそ、身にしみて、心あらん友もがなと、都恋しう覚ゆれ。
満月で曇りないものを、千里はなれた向こうまで(照らす月光を)眺めているよりも、明け方近くになって待ちこがれた末に出た月が、たいそう趣深く、青みがかっているようで、深い山の杉の梢に見えている(様子)、木の間からもれる月の光や、ふっと時雨を降らせている一群の雲に隠れているほど(の月)が、このうえなくしみじみとした趣がある。椎柴や白樫などの濡れているような葉の上に(月光が)きらめいているのが、身にしみて、情趣を解するような友がほしいものだと、都がなつかしく思われる。
すべて、~
すべて、月・花をば、さのみ目にて見るものかは。春は家を立ち去らでも、月の夜は閨のうちながらも思へるこそ、いと頼もしう、をかしけれ。
すべて、月や花を、そのように目だけで見るものか、いや、そうではない。春は家を立ち去らなくても、月の夜は寝床のなかであっても、(それらを)思っていることが、たいそう楽しみで、趣深いものである。
よき人は、~
よき人は、ひとへに好けるさまにも見えず、興ずるさまも等閑なり。片田舎の人こそ、色濃く万はもて興ずれ。
教養があり情趣を解する人は、むやみに風流を好んでいるようにも見えず、楽しむ様子もあっさりしている。田舎者こそ、しつこく万事を面白がるものだ。
花の本には、~
花の本には、ねぢ寄り立ち寄り、あからめもせずまもりて、酒のみ、連歌して、はては、大きなる枝、心なく折り取りぬ。泉には手足さし浸して、雪には下り立ちて跡つけなど、万の物、よそながら見る事なし。
(桜の)花のもとに、にじり寄って立ち寄り、よそ見もしないでじっと見つめて、酒を飲み、連歌をして、最後には、大きな枝を、心なく折り取ってしまう。泉には手や足を浸して、雪には下り立って足跡をつけるなど、万物を、離れたままで見るということがない。