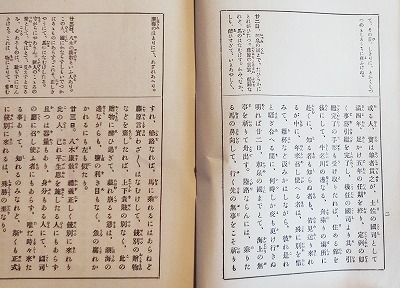『大鏡』より、「肝だめし(道長の豪胆)」の現代語訳です。
四条の大納言のかく何事もすぐれ、~
四条の大納言のかく何事もすぐれ、めでたくおはしますを、大入道殿、「いかでか、かからむ。うらやましくもあるかな。わが子どもの、影だに踏むべくもあらぬこそ、口惜しけれ。」と申させたまひければ、中関白殿、粟田殿などは、げにさもとやおぼすらむと、恥づかしげなる御気色にて、ものものたまはぬに、この入道殿は、いと若くおはします御身にて、「影をば踏まで、面をやは踏まぬ。」とこそ仰せられけれ。まことにこそさおはしますめれ。内大臣殿をだに、近くてえ見たてまつりたまはぬよ。
四条大納言【藤原公任】がこのように何事にも優れて、立派でいらっしゃるのを、大入道殿【藤原兼家】は、「どうして、(公任は)こうであるだろうか【このように優れているのだろうか】。うらやましいことだなあ。私の子どもたちが、(公任の)影さえ踏むこともできないことが、残念だ。」と申し上げなさったところ、中関白殿【藤原道隆】や粟田殿【藤原道兼】などは、本当にそのように(父・兼家が)お思いになっているだろうと、恥ずかしそうなご様子で、ものもおっしゃらないが、この入道殿【藤原道長】は、たいそう若くいらっしゃる御身でありながら、「(公任の)影を踏まないで、顔を踏まないことがあろうか、いや、踏んでやろう。」とおっしゃった。(今の道長は)本当にそのようでいらっしゃるようだ。(今の公任は、道長どころか、道長の息子の)内大臣殿【藤原教通】でさえ(地位の違いから)近くで拝見することがおできにならないことよ。
さるべき人は、~
さるべき人は、とうより御心魂のたけく、御守りもこはきなめりとおぼえはべるは。花山院の御時に、五月しもつ闇に、五月雨も過ぎて、いとおどろおどろしくかきたれ雨の降る夜、帝、さうざうしとやおぼしめしけむ、殿上に出でさせおはしまして、遊びおはしましけるに、人々物語申しなどしたまうて、昔恐ろしかりけることどもなどに申しなりたまへるに、「今宵こそいとむつかしげなる夜なめれ。かく人がちなるにだに、気色おぼゆ。まして、もの離れたる所などいかならむ。さあらむ所に、一人往なむや。」と仰せられけるに、「えまからじ。」とのみ申したまひけるを、入道殿は、「いづくなりとも、まかりなむ。」と申したまひければ、さるところおはします帝にて、「いと興あることなり。さらば行け。道隆は豊楽院、道兼は仁寿殿の塗籠、道長は大極殿へ行け。」と仰せられければ、よその君達は、「便なきことをも奏してけるかな。」と思ふ。
そうであるはずの人【後年出世するのが当然の人(道長のような人)】は、早くから御精神力が強く、(神仏の)ご加護も強いものであるようだと思われますよ。花山院の御時代に、五月下旬の闇夜【月のない夜】に、五月雨【梅雨の時期】も過ぎて、たいそう気味が悪く雨雲が垂れ込めて雨が降る夜、帝は、物足りない【することがなくてつまらない】とお思いになったのだろうか、殿上(の間)におでましになられて、管絃の演奏などでお遊びになっていらっしゃったところ、人々がお話を申し上げるなどしなさって、昔恐ろしかったことなどに移りなさったときに、「今夜はたいそう気味が悪そうな夜であるようだ。このように人がたくさんいてさえ、不気味な気配を感じる。まして、(人がいるところから)離れている所などはどうであろう。そのような所に、一人で行けるだろうか。」とおっしゃったところ、「とても参ることはできないだろう。」とだけ(人々が)申し上げなさったが、入道殿は、「どこへでも、きっと参ろう。」と申し上げなさったので、そのようなところ【そのようなことを面白がるところ】がおありになる帝で、「たいそうおもしろいことである。それならば行け。道隆は豊楽院へ、道兼は仁寿院の塗籠、道長は大極殿へ行け。」とおっしゃったので、ほかの君達は、「(道長は)都合の悪いことを申し上げたことだなあ。」と思う。
また、承らせたまへる殿ばらは、~
また、承らせたまへる殿ばらは、御気色変はりて、「益なし。」とおぼしたるに、入道殿は、つゆさる御気色もなくて、「私の従者をば具しさぶらはじ。この陣の吉上まれ、滝口まれ、一人を『昭慶門まで送れ。』と仰せごと賜べ。それより内には一人入りはべらむ。」と申したまへば、「証なきこと。」と仰せらるるに、「げに。」とて、御手箱に置かせたまへる小刀申して立ちたまひぬ。いま二ところも、苦む苦むおのおのおはさうじぬ。
また、(花山院の命令を)お受けになられた殿たち【道隆・道兼】は、お顔色が変わって、「困ったことだ。」とお思いになっていますが、入道殿【道長】は、少しもそのようなご様子もなくて、「私の家来は連れて行きますまい。この(近衛の)陣の吉上でも、滝口(の武士)でも、誰か一人に、『(道長を)昭慶門まで送れ。』とご命令をお下しください。そこから内へは一人で入りましょう。」と申し上げなさると、(帝は)「(一人だと、大極殿まで行ったかどうか)証拠がないことだ。」とおっしゃるので、「なるほど。」と思って、御手箱に置いていらっしゃる小刀をいただいてお出かけになった。もうお二方も、苦い顔をしながら【しぶしぶ】それぞれお出かけになった。
「子四つ。」と奏して、~
「子四つ。」と奏して、かく仰せられ議するほどに、丑にもなりにけむ。「道隆は、右衛門の陣より出でよ。道長は承明門より出でよ。」と、それをさへ分かたせたまへば、しかおはしましあへるに、中関白殿、陣まで念じておはしましたるに、宴の松原のほどに、そのものともなき声どもの聞こゆるに、術なくて帰りたまふ。粟田殿は、露台の外まで、わななくわななくおはしたるに、仁寿殿の東面の砌のほどに、軒とひとしき人のあるやうに見えたまひければ、ものもおぼえで、「身の候はばこそ、仰せ言も承らめ。」とて、おのおの立ち帰り参りたまへれば、御扇をたたきて笑はせ給ふに、入道殿は、いと久しく見えさせたまはぬを、「いかが。」と思し召すほどにぞ、いとさりげなく、ことにもあらずげにて、参らせたまへる。
「子四つ。」と(宿直の役人が)帝に申し上げ、このようにおっしゃって相談しているうちに、丑の刻にもなったのだろう。「道隆は右衛門の陣から出でよ。道長は承明門から出でよ。」と、それ(出発するところ)までもお分けになったので、そのとおりにしていらっしゃったが、中関白殿【道隆】は、(右衛門の)陣までは我慢していらっしゃったが、宴の松原のあたりで、得体のしれない声々が聞こえたので、どうしようもなくてお帰りになる。粟田殿【道兼】は、露台の外まで、ぶるぶる震えていらっしゃったが、仁寿殿の東面の砌【軒下の石畳】のあたりに、軒(の高さ)と同じ大きさの人がいるようにお見えになったので、正気ではいられず、「体がございますからこそ、ご命令もお受けすることができよう。」といって、それぞれ引き返してまいりなさったので、(帝は)御扇をたたいてお笑いになったが、入道殿【道長】は、たいそう長いことお見えにならないので、「どうしたのか。」とお思いになっているうちに、たいそうさりげなく、何事でもないような様子で、(帰って)まいりなさった。

「子の刻」は、「午後11時~午前1時」で、「四つ」は、それを4分割した最後の時間帯を指します。つまり、「午前0時30分~午前1時ごろ」になります。
「丑の刻」は、「午前1時~午前3時」で、ここでは「丑にもなりにけむ」という表現から、「丑の刻の最初のほう」であると考えられますので、3人が肝だめしに出かけたのは「午前1時~午前2時」のころだと思われます。
「いかにいかに。」と問はせたまへば、~
「いかにいかに。」と問はせたまへば、いとのどやかに、御刀に、削られたる物を取り具して奉らせたまふに、「こは何ぞ。」と仰せらるれば、「ただにて帰り参りてはべらむは、証さぶらふまじきにより、高御座の南面の柱のもとを削りてさぶらふなり。」と、つれなく申したまふに、いとあさましくおぼしめさる。こと殿たちの御気色は、いかにもなほ直らで、この殿のかくて参りたまへるを、帝よりはじめ感じののしられたまへど、うらやましきにや、またいかなるにか、ものも言はでぞさぶらひたまひける。
「どうであった。どうであった。」と(帝が)お尋ねになると、(道長は)たいそう落ち着いて、御刀に、削られた物を取り添えて差し上げなさるので、「これは何だ。」とおっしゃると、「手ぶらで帰ってまいりましたら、(実際に行った)証拠がございますまいから、高御座の南面の柱の下を削ってございます。」と、平然と申し上げなさるので、(帝は)たいそう驚きあきれる思いをしなさる。他の殿たち【道隆・道兼】のお顔色は、どのようにしてもやはり直らず、この殿【道長】がこのように帰ってまいられたのを、帝をはじめ(周囲の者が)感心してほめそやしなさるが、うらやましいのだろうか、それともどういう気持ちなのだろうか、ものも言わずに控えていらっしゃった。
なほ疑はしく思し召されければ、~
なほ疑はしくおぼしめされければ、つとめて、「蔵人して、削りくづをつがはしてみよ。」と仰せごとありければ、持て行きて、押しつけて見たうびけるに、つゆ違はざりけり。その削り跡は、いとけざやかにてはべめり。末の世にも、見る人はなほあさましきことにぞ申ししかし。
(帝は)それでもやはり疑わしくお思いになったので、翌朝、「蔵人に(命じて)、削り屑を(柱の削り跡に)あてがわせてみよ。」というお命じがあったので、(蔵人が)持って行って、(柱の削り跡に)押しつけて見なさったところ、少しも違わなかった。その削り跡は、たいそうはっきりとしているようでございます。後の世にも、(削り跡を)見る人はやはり驚きあきれることだと申したことだ。