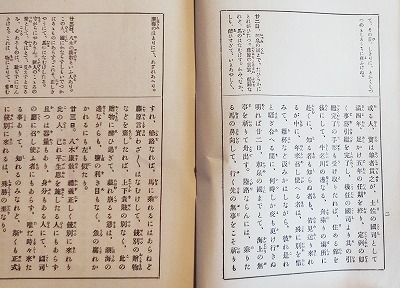添えて・・・
意味
(1)【添加】 (そのうえ)~までも
(2)【類推】 ~でさえも *中世以降の用法
(3)【限定】 ~だけでも *中世以降の用法
ポイント

「さへ」は、動詞「添ふ」の連用形「そへ」が音変化したものと見られています。
「添」が示すとおり、根本的な意味は【添加】なので、まずは「(そのうえ)~までも」と訳してみるのがよいです。

それに【類推】や【最小限の限定】などの意味も加わってくるんだね。

もともと「付け加え」の意味なので、
AよりもさらにあってもおかしくないBがない。(だからAがあるはずがない)
というような文意での【類推】の用法や、
現状にひとつだけ加えたAが、せめてあればいいのになあ
というような文意での【最小限の限定】の用法などが発生してきます。
中古ではこの「類推」「最小限の限定」の意味は「だに」が担っていましたが、中世では「さへ」に吸収されていき、「だに」の使用が減っていきました。
いったん「だに」が盛り返すのですが、最終的には「さへ」が広く使用されていきます。

「類推」だと、「すら」っていうのもあったよね。

これがややこしいのですが、奈良時代には、
「だに」⇒「限定」
「すら」⇒「類推」
「さへ」⇒「添加」
という役割の区別がありました。
ところが、平安時代になると、「だに」が「類推」の意味でも使用されるようになり、そのぶん「すら」があまり使われなくなっていきます。
〈平安時代〉
「だに」⇒「限定」「類推」
「すら」⇒和歌や和漢混交文でないと使われない
「さへ」⇒「添加」
さらに、鎌倉時代になると、「だに」の登場回数が減り、そのぶん「だに」の機能が「さへ」に乗り移ってきます。
〈鎌倉時代以降〉
「だに」⇒次第に使用数が減る
「さへ」⇒「添加」「限定」「類推」

ああ~。
「さへ」についていえば、上代・中古は「添加」の意味だけど、中世から3つの用法になっていくと考えればOKかな。

だいたいそれで大丈夫です。
出典が平安中期の作品なのであれば、「添加」で決め打ちして、「(そのうえ)~までも」の意味でとりましょう。

現代語だと、
【添加】風が冷たい中、雨さえも降ってきた。
【類推】AIにはプロでさえ勝てない。(まして素人が勝てるはずがない)
【限定】せめて500円さえあれば、弁当が買えたのになあ。
というように、まさに3つとも残っているね。

たしかに、現代文法だとその3つですね。
現代語だと、もともとの意味の「添加」の用法がいちばん少ない気がしますね。
例文
その夜、雨風、岩をも動くばかり降りふぶきて、神さへ鳴りてとどろくに、(更級日記)
(訳)その夜、雨風が、岩をも動かすほどに降り、ふぶいて、そのうえ雷までも鳴って(雷鳴が)とどろくときに、

「添加」の使い方ですね。
中古の作品は「添加」で解してください。
前の世にも御契りや深かりけん、世になく清らなる玉の男御子さへ生まれたまひぬ。(源氏物語)
(訳)(帝と桐壺更衣は)前世でもご宿縁が深かったのであろうか、(深いご寵愛に加えて)この世にないほど美し美しい玉のような男御子までもお生まれになった。

「添加」の使い方ですね。
まさしき兄弟さへ、似たるは少なし。まして従兄弟に似たるものはなし。(曽我物語)
(訳)本当の兄弟でさえも、似ている者は少ない。まして従兄弟に似ている者はいない。

「類推」の使い方ですね。
命さへ あらば見つべき 身のはてを しのばん人の なきぞかなしき (新古今和歌集)
(訳)せめて(あなたの)命だけでもあったなら、きっと見届けるはずの私の最期を、思い起こすような人がいないのが悲しい。

「和泉式部」の歌です。
「さへ」は、「限定」の用法で用いられており、「最小限の希望」を意味しています。
これは本来「だに」の役割ですが、鎌倉時代後半くらいから「さへ」がその意味も担っていきました。

でも、「和泉式部」って「藤原兼家」の妻でしょう。
平安時代中期ド真ん中の人じゃないか。

出典は『新古今和歌集』なので、鎌倉時代の編集になります。
この歌は『和泉式部集』では、
命だに あらばみるべき 身の果てを 偲ばむ人も なきぞ悲しき
となっていて、こちらは「だに」なんですよね。
『新古今和歌集』の読者にとっては、この「だに」が「さへ」になっても、歌全体として同じ意味になったということですから、「さへ」の意味が広がっていったことを示していると思います。