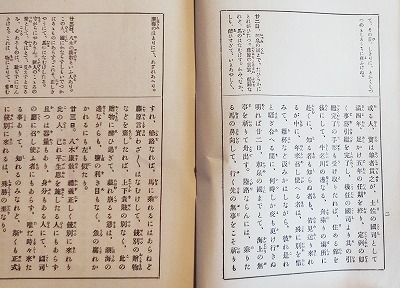『枕草子』より、「殿などのおはしまさで後」の現代語訳です。
殿などのおはしまさで後、~
殿などのおはしまさで後、世の中に事出で来、騒がしうなりて、宮も参らせたまはず、小二条殿といふ所におはしますに、何ともなく、うたてありしかば、久しう里に居たり。御前わたりのおぼつかなきにこそ、なほ、え絶えてあるまじかりけれ。
殿【藤原道隆】がお亡くなりになったのち、世の中にさまざまな事件が起こり、騒がしくなって、中宮【定子】も参内なさらず、小二条殿という所にいらっしゃる折に、(私も)何ということもなく、いやな気持ちであったので、長い間実家にいた。(しかし、中宮定子の)おそばのあたりが気がかりなので、やはり、縁を切ったままでは【このまま出仕しないでは】いられそうもなかった。
右中将おはして物語したまふ。~
右中将おはして物語したまふ。「今日、宮に参りたりつれば、いみじうものこそあはれなりつれ。女房の装束、裳・唐衣折に合ひ、たゆまで候ふかな。御簾のそばの開きたりつるより見入れつれば、八、九人ばかり、朽葉の唐衣、薄色の裳に、紫苑・萩など、をかしうて居並みたりつるかな。
右中将【源経房】がいらっしゃってお話をなさる。「今日、中宮様(の御殿)に参上したところ、たいそうしみじみと趣き深かった。女房の装束は、裳も、唐衣も、季節に合って、怠らずにお仕えしているよ。御簾のそばの開いているところから(中の様子を)のぞいたところ、八、九人ほど、朽葉の唐衣を着て、薄紫色の裳に、紫苑、萩など(のかさねも着て)、趣がある様子で並んで座っていたよ。
御前の草のいと繁きを、~
御前の草のいと繁きを、『などか。かき払はせてこそ。』と言ひつれば、『ことさら露置かせて御覧ずとて。』と、宰相の君の声にていらへつるが、をかしうもおぼえつるかな。『御里居、いと心憂し。かかる所に住ませたまはむほどは、いみじきことありとも、必ず候ふべきものに思しめされたるに、効なく。』と、あまた言ひつる、語り聞かせたてまつれとなめりかし。参りて見たまへ。あはれなりつる所のさまかな。対の前に植ゑられたりける牡丹などの、をかしきこと。」などのたまふ。
御前の庭の草がたいそう繁っているので、『どうして(繁ったままにしているの)か。刈り取らせては(いかがか)。』と言ったところ、『わざわざ(草に)露を置かせて(中宮様が)御覧になるといって。』と、宰相の君の声で答えたのが、趣きあることと思われたよ。(女房たちが)『(清少納言が)郷里にいるのは【実家に戻っているのは】、たいそう情けない。(中宮様が)このような所に住んでいらっしゃるようなときは、とてもいやなことがあっても、必ずおそばにお仕えするはずの人であると(中宮様は)お思いになっているのに、そのかいもなく。』と、大勢で言っていたのは、(あなたに)「語り聞かせ申し上げよ」ということであるようだよ。参上して(その場所を)ご覧なさい。しみじみと趣き深い所の様子であるよ。対の屋の前に植えられていた牡丹などの、美しいこと。」などとおっしゃる。
「いさ、人のにくしと思ひたりしが、~
「いさ、人のにくしと思ひたりしが、また憎くおぼえはべりしかば。」といらへきこゆ。「おいらかにも。」とて笑ひたまふ。
(私は)「いいえ。人【女房たち】が(私を)憎らしいと思っていたことが、こちらもまた憎らしく思われましたので(参上しない)。」とお答え申し上げる。(経房は)「おだやかに【穏便に】。」と言ってお笑いになる。
げにいかならむと思ひまゐらする御気色にはあらで、~
げにいかならむと思ひまゐらする御気色にはあらで、候ふ人たちなどの、「左の大殿方の人、知る筋にてあり。」とて、さし集ひものなど言ふも、下より参る見ては、ふと言ひやみ、放ち出でたる気色なるが、見馴らはず憎ければ、「参れ。」など、たびたびある仰せ言をも過ぐして、げに久しくなりにけるを、また、宮の辺には、ただあなた方に言ひなして、空言なども出で来べし。
本当に(中宮様は)どのよう(にお過ごし)であろうかと思い申し上げる(これほど心配している)中宮様のご様子(が出仕しない理由)なのではなくて、(中宮様の)おそばにお仕えする人たち【女房たち】などが、「左大臣方の人【藤原道長寄りの人】が、(私の)親しい関係である。」と言って、集まって話などをする時も、(私が)局から参上するのを見ると、急に話をやめ、のけ者にしている様子であるのが、(今まで)見慣れないことで憎らしいので、「参上せよ。」などと、たびたびある(中宮様の)仰せ事【おことば】をもそのままにして、(参上しない期間が)実に長い間になってしまったが、(そのことを)また中宮様の周辺では、ひたすら(私を)向こう側【左大臣方】(の人間)とことさらに言って、事実ではないうわさなどもきっと出てくるだろう。

げにいかならむと思ひまゐらする御気色にはあらで、候ふ人たちなどの、~憎ければ、
という部分は、やや意訳すると、
「(私自身あれこれ考えている)中宮様のご様子は(私が出仕する、しないということに)関係なくて、お仕えする女房たちが(いろいろうるさくて)憎らしいから、(参上していない)」
という展開になります。
テキストによっては、「げにいかならむと思ひまゐらする。御気色にはあらで、」というように、連体止めのように「まゐらする」で結ばれていて、いったん文意が切れているという解釈もあります。
(古文にもともと句読点はなく、文構造から仮説して後世で句読点を打っているので、いまだに解釈が分かれているところはたくさんあります。)
さて、その場合、
「本当に(中宮様は)どのよう(にお過ごし)だろうと思い申し上げる。(ただ、私が出仕しないのは、中宮様の)ご意向ではなくて、
といったように訳すことができます。
例ならず、~
例ならず、仰せ言などもなくて日ごろになれば、心細くてうち眺むるほどに、長女、文を持て来たり。「御前より、宰相の君して、忍びて賜はせたりつる。」と言ひて、ここにてさへひき忍ぶるもあまりなり。人づての仰せ書きにはあらぬなめりと胸つぶれて、疾く開けたれば、紙にはものもかかせたまはず、山吹の花びらただ一重を包ませたまへり。
いつもと違って、(中宮様の)仰せ事【おことば】などもなくて数日間になったので、心細くてもの思いに沈んで(外を)ぼんやり眺めるうちに、長女が、手紙を持って来た。「中宮様から、宰相の君を通して、こっそりとくださった。」と言って、ここ【清少納言の実家】でまでも人目を避けるのも度をこしている。(女房などによる)代筆のお手紙ではないようであると胸がしめつけられて、すぐに開けたところ、紙には何もお書きになならず、山吹の花びらただ一枚をお包みになっている。
それに、~
それに、「言はで思ふぞ」と書かせたまへる、いみじう、日ごろの絶え間嘆かれつる、皆慰めてうれしきに、長女もうちまもりて、「御前には、いかが、ものの折ごとに思し出できこえさせたまふなるものを。誰も、あやしき御長居とこそ侍るめれ。などかは参らせたまはぬ。」と言ひて、「ここなる所に、あからさまにまかりて、参らむ。」と言ひて往ぬるのち、御返り言書きて参らせむとするに、この歌の本、さらに忘れたり。
それに、「言はで思ふぞ」とお書きになっているのが、たいそうすばらしく、ここ数日の(仰せ事のお言葉が)ない期間をふと悲しく思ったことも、すっかり気分が晴れてうれしく思っていると、長女【雑用をする女官】も(私を)じっと見つめて、「中宮様には、どんなにか、何かの折々に(あなたを)思い出し申し上げなさるということであるのに。誰もが、妙に長いお里下がりと思うようでございます。どうして(お返事を)差し上げなさらないのか、いや、差し上げなさるべきだ。」と言って、「この近所に、ほんのちょっとの間退出して、(すぐにまたここに)参上しよう。」と言って去ったあと、(中宮様に)ご返事を書いて差し上げようとするが、この歌【言はで思ふぞ】の本【上の句】を、すっかり忘れている。

長女のセリフの「などかは参らせたまはぬ」というところは、「どうして宮中に参上なさらないのか、いや、参上なさるべきだ」と訳している解説書が多いです。
ただ、そうすると、「参る+す+たまふ」という構造になり、「す」は「尊敬」の助動詞ということになります。つまり、「せたまふ」が「二重尊敬(最高敬語)」という扱いになります。
直前に「中宮定子」に対する「させたまふ」がありますので、「清少納言」に対する「参らせたまはぬ」の「せたまふ」を「二重尊敬」と解すると、同じセリフの中に「中宮定子」と「清少納言」に「同じ次元の敬語表現」を使用していることになります。
会話文なので厳密なルールはないのですが、「中宮定子」と「清少納言」に同列の敬語表現を適用するのは、違和感が残ります。
さらに、長女は、「ちょっと退出して、また参ります」と言って出ていき、そのタイミングで清少納言は「御返り事書きて参らせむ」とするわけです。

ああ~。
つまり「長女」は、「なんでお返事くらい書かないの? いや、さすがに書くべきでしょ! ちょっとどっか行って、また戻ってくるからね(その間に中宮様にお返事くらい書きなされ)」って言っているわけだな。

反語というのは、「強い主張」でもあるので、文脈によっては「指示」や「お願い」のような表現になります。
ここで長女が散歩に出かけたタイミングで、清少納言が「お返事」を書き始めることから考えると、長女のセリフ自体が「お返事くらいお書きください」と言っていると考えたほうがいいように思います。
「いとあやし。~
「いとあやし。同じ古事といひながら、知らぬ人やはある。ただここもとにおぼえながら言ひ出でられぬは、いかにぞや。」など言ふを聞きて、前に居たるが、「『下行く水』とこそ申せ。」と言ひたる、などかく忘れつるならむ。これに教へらるるもをかし。
「たいそう不思議だ。同じ古歌と言っても、(これほど有名な歌を)知らない人がいるだろうか。ただもうここまで(上の句を)思い出しているのに、口に出てこないのは、どうしてなのか。」などと言うのを聞いて、(私の)前に座っていた(童女)が、「『下行く水』と申す。」と言った(歌を)、どうしてこのように忘れてしまっていたのだろう。こんな童女に教えられるのもおもしろい。

「言はでぞ思ふ」「下行く水」という歌は、『古今和歌六帖』にあります
「心には 下行く水の わきかへり 言はで思ふぞ 言ふにまされる」
の歌をさしています。
御返りまゐらせて、~
御返り参らせて、少しほど経て参りたる、いかがと、例よりはつつましくて、御几帳に端隠れて候ふを、「あれは、今参りか。」など、笑はせたまひて、「憎き歌なれど、この折は、さも言ひつべかりけりとなむ思ふを。おほかた見つけでは、しばしも、えこそなぐまじけれ。」などのたまはせて、変はりたる御気色もなし。
ご返事を差し上げて、少し時が経ってから参上したが、(中宮様のご様子は)どうであろうかと、いつもよりは気後れして、(私が)御几帳に少し隠れておそばに控えるのを、「あれは、新参者か。」などと、(中宮様は)お笑いになって、「(「言はで思ふぞ」の歌は)憎らしい歌であるが、この際は、そのように言うべきだなあと思うよ。(あなたを)まったく見ないでは、少しの間も、気持ちが慰められないだろう。」などとおっしゃって、(かつての中宮様と)変わったご様子もない。
童に教へられしことなどを啓すれば、~
童に教へられしことなどを啓すれば、いみじう笑はせたまひて、「さることぞある。あまり侮る古事などは、さもありぬべし。」など仰せらるるついでに、「謎々合はせしける、方人にはあらで、さやうの事にらりやうりやうじかりけるが、『左の一は、おのれ言はむ。さ思ひたまへ。』など頼むるに、さりとも悪きことは言ひ出でじかしと、頼もしくうれしうて、皆人々作り出だし、選り定むるに、『その言葉を、ただ任せて、残したまへ。さ申しては、よもくちをしくはあらじ。』と言ふ。げにと推し量るに、日いと近くなりぬ。
子どもに(上の句を)教えられたことなどを申し上げると、たいそうお笑いになって、「そんなこともある。(知っているものと)あまり侮っている古歌などは、そういうこともきっとあるだろう。」などとおっしゃるついでに、(中宮様がお話なさるには)「謎々合わせをしたとき、片方の人ではなくて、そういった事に物慣れて巧みな人が、『左の一番は、私が(謎を)言おう。そうお思いください。』などと頼らせるので、そうであっても悪い謎は言い出さないだろうと、(皆が)頼もしく(思って)うれしくて、人々が皆(謎を)作り出し、選び定める時、『その言葉を、ただもう(私に)任せて、(謎を決めずに)お残しください。(私が)このように申し上げるからには、まさか残念なことにはなるまい。』と言う。なるほどと(謎合わせの勝ちを)推量するうちに、(謎合わせの)日が近くなった。
『なほ、この言のたまへ。~
『なほ、この言のたまへ。非常に、同じ言もこそあれ。』と言ふを、『さは、いさ知らず。な頼まれそ』などむつかりければ、おぼつかなながら、その日になりて、皆、方の人、男・女、居分かれて、見証の人など、いと多く居並みて合はするに、左の一、いみじく用意してもてなしたるさま、いかなる言を言ひ出でむと見えたれば、こなたの人、あなたの人、皆心もとなくうちまもりて、『なぞ、なぞ。』と言ふほど、心にくし。『天に張り弓』と言ひたり。
『やはり、この(謎々の)言葉をお言いください。万が一、同じ(謎々の)言葉があると困る。』と言うと、『そうであるなら、さあ知らない。頼りにしないでくれ。』などと不機嫌になったので、不安なまま、その日になって、皆、左右片方ずつの人が、男女で分かれて座って、立会い役の人などが、たいそう多く並んで座って(謎を)合わせるのに、左の一番(の人)が、たいそうもったいぶって準備している様子は、どのような(謎の)言葉を言い出すのだろうと見えたので、こちら側の人も、あちら側の人も、皆待ち遠しく見守って、『なぞ、なぞ』と言う様子は、しゃくにさわる。(そして)『天に張り弓』と言った。

「天にある張り弓はなあ~んだ?」というなぞなぞであり、こたえは「上弦の月」「下弦の月」あるいは「三日月」も正解になるといわれるシンプルな問題です。
つまり、子どもでも知っているようななんでもない「なぞなぞ」を出してきたのですね。

「相手に対して、すっげえ最高の謎をしかけっぞ! 私にまかしときゃ勝てっぞ! 余計なことすんなよ」っていう雰囲気だったのに、そいつから提出されたなぞなぞが「ズコー!!」ってずっこけるほど安易なものだったんだな。

野球でたとえるとしたら、「私は最高の変化球を持っているから、私に先発をまかせな。悪いようにはならないから。ほかのやつが投球練習をする必要はないぞ」とか言っておきながら、試合の最初の一球が、誰でも場外ホームランを打てるような棒ダマだったような感じです。
ところがその相手は・・・
右方の人は、~
右方の人は、いと興ありてと思ふに、こなたの人は、ものもおぼえず、皆、憎く、愛敬なくて、あなたに寄りて、ことさらに負けさせむとしけるをなど、片時のほどに思ふに、右の人、『いとくちをしく、をこなり。』と、うち笑ひて、『やや、さらにえ知らず。』とて、口を引き垂れて、『知らぬ言よ。』とて、猿楽しかくるに、籌させつ。『いとあやしきこと。これ知らぬ人は、誰かあらむ。さらに籌ささるまじ。』と論ずれど、『知らずと言ひてむには、などてか、負くるにならざらむ。』とて、次々のも、この人なむ皆論じ勝たせける。
右方の人は、たいそうおもしろい【かんたんに勝てる】と思ったが、こちら側【左方】の人は、呆然として、皆、(一の人が)憎らしく、しゃくにさわって、あちら側【右方】に味方して、わざと(左方を)負けさせようとしたなどと、少しの間に思うが、右の人が、『たいそうがっかりだ、ばかばかしい』と、笑って、『いやいや、(答えは)まったくわからない。』と言って、口元を引き下げて【への字口にして】、『知らないことばよ。』と言って、(猿楽のまねごとで)ふざけているうちに、かず【勝ち負けを数えるのに使う串】を(かず入れに)ささせてしまった。『たいそうおかしなことだ。これ【天に張弓のなぞなぞ】を知らない人は、誰かいるだろうか。これ以上かずをさしてはなるまい。』と議論するが、『知らないと言ってしまうとしたら、どうして、負けにならないだろうか、いや、それは負けである。』と言って、次々の勝負も、この人がみんな議論して(左方を)勝たせた。

あ、あまりにも「安易ななぞなぞ」なもんだから、回答側がニヤニヤしながら「これはわからないなあ~」とかふざけていたら、「はい! わからないって言ったから負け~!」っていう感じで、言葉巧みに自チームを勝ちに導いたんだな。

でもたしかに、定期試験とかでも、あまりにもド直球で簡単な設問だと、「え、かえって引っ掛け問題なんじゃないか」とうたがって、時間かかっちゃうことありますよね。

ある。
いみじく人の知りたることなれども、~
いみじく人の知りたる言なれども、おぼえぬ時は、しかこそはあれ。『何しにかは、知らずとは言ひし。』と、後に恨みられけること。」など語り出でさせたまへば、御前なる限り、「さ思ひつべし。くちをしういらへえけむ。」「こなたの人の心地、うち聞き始めけむ、いかが憎かりけむ。」なんど笑ふ。これは、忘れたることかは。ただ皆知りたることとかや。
たいそう人が知っていることだけれども、覚えていない時は、このようなものである。『どうして、知らないと言ったのか。』と、(しっかり答えなかった人は)後に恨まれたこと。」などとお話し出しなさると、(中宮様の)御前にいる限り(の女房たち)は、「きっとそう思うだろう。残念な答えをしたものだ。」「こちら側【左方】の人の気持ちは、(このなぞなぞを)はじめに聞いた時、どんなに憎らしかっただろう。」などと笑う。これは、忘れてしまったことだろうか、いや、忘れていたわけではない。ただ皆が知っている(から答えなかった)ことだろう。

清少納言が、有名な歌の上の句を忘れてしまっていたというエピソードに対して、中宮定子は、「誰でも答えられるような言葉を言わないケース」の話をします。

「だからあんたも忘れたわけじゃなくて、言わなかっただけでしょ」って言いたいのかな?

「そんなふうに中宮様がフォローしてくれたんですよ」っていうことは言いたいのでしょうね。
ただ、この時の清少納言は、「伊周サイド」と対立関係にある「道長サイド」に通じているとうわさされていましたから、伊周の妹である中宮定子の周辺の人は、清少納言に対して「うたがい」や「にくらしさ」の情を持っていたとされています。
清少納言が「有名な歌」にかこつけて「忘れてしまった」というエピソードを語ることに対して、中宮定子が「なぞなそ」のエピソードで「知りすぎていて言えないこともある」という話をするというのは、清少納言の立場を慮って、「そのままでいい」と暗に言っているような深みを感じます。
いずれにせよ、清少納言が語る中宮定子は教養と配慮にあふれた人物像として一貫していますから、ここでも何らかの意図で定子を讃嘆する含意があるのだと思います。