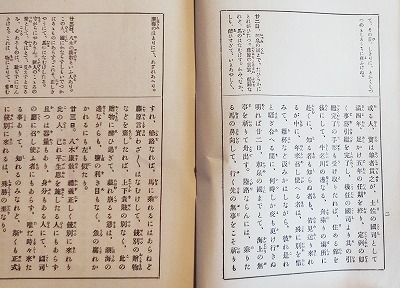「の」「が」という格助詞が〈主格〉で使用されるとき、
AのB。 (AがBする。)
というシンプルな構成で一文が完結することはほとんどありません。
基本的には、その「外側」に、「大きな文」の主語と述語があると考えましょう。
想定されるのは次の2パターンです。
パターンA
〈大主語〉 〈小主語〉の(が)〈小述語〉 〈大述語〉
というように、「〈小主語〉の〈小述語〉」「〈小主語〉が〈小述語〉」という主述構造の外側に、〈大主語〉〈大主語〉が実質上存在しているのです。
ただし、日本語では主語は積極的に省かれるので(そもそも主語という概念自体が希薄なので)、〈大主語S〉は書かれない傾向にあります。そのことから、
〈小主語〉の(が)〈小述語〉 〈大主語〉
という構文になりやすくなります。たとえば、次のような文です。
童 部 の 踏み明けたる築泥の崩れより通ひけり。
〈小主語〉 〈小述語〉 〈大述語〉
「踏み明けたる」の主語は「童部」です。しかし、これは〈築泥の崩れ〉という体言に回収されていき、〈書かれていない誰か〉が〈築泥の崩れ〉から「通った」という構文になります。
〈書かれていない誰か〉が、ここでいう〈大主語〉です。このように〈大主語〉は、書かれていないことが多くなります。書かれる場合は、基本的に〈小主語〉よりも前に書かれます。
またこの例のように、〈主格〉の「の」「が」によって導かれる〈小述語〉は、体言に係っていくケースがほとんどなので、多くは連体形になります。かつまた、その体言は省略されやすい傾向にあります。すると、次のような例文になります。
男 君 の 来ずなりぬる、すさまじきなり。
〈小主語〉 〈小述語〉 〈大述語〉
これは、「男君が来なくなったこと(に対して)、興ざめである(と思った)」ということである。本来であれば「来ずなりぬる」の直後に「こと」が存在しますが、古文では「こと」「もの」「さま」は省略されやすいので、ここでも省かれています。
「すさまじきなり」というのは、〈書かれていない誰か〉の感想です。つまりこれが文全体の述語〈大述語〉です。
場合によっては、〈大述語〉すら省略されることもあります。次のような例文です。
雀の子を 犬 君 が 逃がしつる。
〈小主語〉 〈小述語〉
係り結びでもないのに、文末が連体形になっています。
これは、「~逃がした(ことが残念だ)」というように、本来であれば書かれたはずの〈体言〉及び〈大述語〉が、両方とも省略されているケースなのです。
状況から考えて、述語は「残念・悲しい」といった感情になることが推論できます。書かれていない〈大主語〉は、発話者自身です。
同じような例をもう一つ見てみましょう。
み吉野の山の白雪踏み分けて入りにし 人 の おとずれもせぬ
〈小主語〉 〈小述語〉
これは、「吉野山の白雪を踏み分けて山に入ってしまった人が、手紙もよこさない」という意味です。
これも、文末が「ず」という終止形ではなく、連体形「ぬ」になっていますね。
これは、「~手紙もよこさない(ことが寂しい)」といったように、〈体言〉及び〈大述語〉が両方とも省略されているのです。
〈大述語〉に該当するのは、「寂しい・悲しい」といった感情です。書かれていない〈大主語〉は、和歌の詠み手自身です。
以上のように、「〈主語〉の〈述語〉」「〈主語〉が〈述語〉」という構造は、一見、「文全体の主語・述語」に見えることがあっても、基本的にはその外側に、〈大主語〉〈大述語〉が控えていると考えられるとよいのです。
これは、主体判定をするときに重要な思考になります。
ただし、〈大主語S〉に関しては、いつもいつも外側に別の人物が存在するとは限らない。それが次の〈パターンB〉です。
パターンB
例文から見てみましょう。
火 の 燃え立つも見ゆ。
〈小主語〉〈小述語〉
ここでは、「燃え立つ」の後に「さま」などが省略されています。
「見ゆ」は「(~が)見える」「(~が)現れる」という意味ですから、次のように訳します。
火が燃え立つ様子も見える。
つまり、「〈小主語〉が〈小述語〉」という構造が係っていく体言自体が、主語になっているのです。そのようなケースもあると覚えておきましょう。