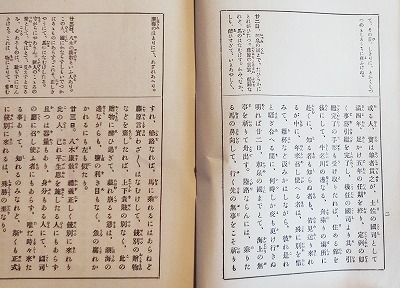『竹取物語』より、翁がかぐや姫にたいして、求婚者たちを見定めて結婚するように説得する場面です。
人の物ともせぬ所に惑ひ歩けども、~
人の物ともせぬ所に惑ひ歩けども、何のしるしあるべくも見えず。家の人どもに物をだにいはむとて、いひかくれども、ことともせず。あたりを離れぬ君達、夜を明かし、日を暮らす、多かり。おろかなる人は、「用なき歩きは、よしなかりけり」とて来ずなりにけり。
(かぐや姫を見に来た人々は)人が問題にしないような所まで心を乱しながら動き回るが、何の効き目があるだろうとも見えない。家の使用人たちに、せめて何か言うだけでもと、話しかけるが、(使用人も)取り扱わない。家の近くを離れない君達は、夜を明かし、日中も(そこで)過ごす者が多い。いいかげんな人は、「用もなくあちこと動き回るのは、よくなかった」と言って来なくなった。
その中に、~
その中に、なほいひけるは、色好みといはるるかぎり五人、思ひやむ時なく、夜昼来けり。その名ども、石作りの皇子、くらもちの皇子、右大臣安倍御主人、大納言大伴御行、中納言石上磨足、この人々なりけり。
その中に、それでもなお(会いたいと)言い続けたのは、好色と言われるほどの五人で、(かぐや姫への)思いが消える時がなく、夜も昼もやって来た。その名は、石作りの皇子、くらもちの皇子、右大臣阿倍御主人、大納言大伴御幸、中納言石上磨足、この人々だった。
世の中に多かる人をだに、~
世の中に多かる人をだに、すこしもかたちよしと聞きては、見まほしうする人どもなりければ、かぐや姫を見まほしうて、物も食はず思ひつつ、かの家に行きて、たたずみ歩きけれど、甲斐あるべくもあらず、文を書きて、やれども、返りごともせず。わび歌など書きておこすけれども、甲斐なしと思へど、十一月、十二月の降り凍り、六月の照りはたたくにも、障らず来たり。
(この五人は)世の中にありふれた人でさえ、すこしでも容貌がよいと聞けば、見たがる【結婚してわがものにしたがる】人たちだったので、かぐや姫を見たがって【手に入れたがって】、食事もせず、思いを募らせながら、あの(かぐや姫の)家に行って、たたずんだり、歩き回ったりしたが、効果があるはずがなく、手紙を書いて、送るが、(かぐや姫は)返事もしない。ものわびしい歌を書いて送ったが、効果はないと思うが、十一月、十二月の雪が降り氷がはるときにも、六月の陽光が照り付け雷鳴がとどろく時にも、(この五人の男たちは)支障なくやって来た。
この人々、~
この人々、在る時は、たけとりを呼びいでて、「娘を我に賜べ」と、伏し拝み、手をすりのたまへど、「おのが生さぬ子なれば、心にもしたがはずなむある」といひて、月日すぐす。かかれば、この人々、家に帰りて、物を思ひ、祈りをし、願を立つ。思ひ止むべくもあらず。「さりとも、つひに男あはせざらむやは」と思ひて頼みをかけたり。あながちに、心ざしを見え歩く。
この人々は、ある時は、竹取の翁を呼び出して、「娘を自分にください」と、伏し拝み、手をすり合わせておっしゃるが、(翁は)「自分の生み出した子ではないので、思い通りにはならない」と言って、そのまま月日を過ごす。こういうわけで、この人々は、家に帰って、物思いにふけり、(神仏に)祈り、願をかける。(かぐや姫への)思いは止めることができない。「そうはいっても、最後まで【一生涯】男に会わせない【結婚させない】だろうか、いや、そんなことはなかろう」と思って、期待していた。ことさらに、(かぐや姫に対する)切なる思いを見せるように歩き回る。
これを見つけて、~
これを見つけて、翁、かぐや姫にいふやう、「我が子の仏、変化の人と申しながら、ここら大きさまでやしなひたてまつる心ざしおろかならず。翁の申さむこと、聞きたまひてむや」といへば、かぐや姫、「何事をか、のたまはむことは、うけたまはらざらむ。変化の者にてはべりけむ身とも知らず、親とこそ思ひたてまつれ」といふ。翁、「嬉しくものたまふものかな」といふ。
これを見つけて、翁が、かぐや姫に言うことには、「私の大切な人よ、(あなたは)変化の人と申しますが、これほどの大きさになるまで養育し申し上げる(私の)気持ちはいいかげんではない。翁の申すこと、お聞きになってくれるか」と言うと、かぐや姫は、「何事でも、おっしゃることは、うかがわないだろうか、いや、何でもうかがおう。変化の者でありますとかいう身のほどをも知らず、親とばかり思い申し上げているのに」と言う。翁は「嬉しいことをおっしゃるのだな」と言う。
「翁、年七十に余りぬ。~
「翁、年七十に余りぬ。今日とも明日とも知らず。この世の人は、男は女にあふことをす。女は男にあふことをす。その後なむ門広くもなりはべる。いかでかさることなくてはおはせむ」。
「翁は、七十歳を過ぎた。(命の終わりは)今日とも明日ともわからない。この世の中の人は、男は女と結婚する。女は男と結婚する。その後に一門は繫栄するのです。どうしてそのようなこと(結婚すること)がなくていらっしゃるだろう」。
かぐや姫のいはく、~
かぐや姫のいはく、「なんでふ、さることかしはべらむ」といへば、「変化の人といふとも、女の身持ちたまへり。翁の在らむかぎりはかうてもいますがりなむかし。この人々の年月を経て、かうのみいましつつのたまふことを、思ひさだめて、一人一人にあひたてまつりたまひね」といへば、かぐや姫のいはく、「よくもあらぬかたちを、深き心も知らで、あだ心つきなば、後くやしきこともあるべきを、と思ふばかりなり。世のかしこき人なりとも、深き心ざしを知らでは、あひがたしとなむ思ふ」といふ。
かぐや姫の言うことには、「どうして、そのようなこと(結婚)をするのでしょうか」と言うと、「変化の人と言っても、(あなたは)女の身をお持ちでいる。翁のいるような間はこのままでもいらっしゃれよう。この(五人の)人々が年月を経て、これだけおいでになりおっしゃることを、判断して、(そのうちの)一人と結婚し申し上げなさいませ」と言うと、かぐや姫の言うには、「よいというわけでもない容貌なのに、心の深さもわからないで(結婚して)、浮気心を抱いたら、後になって悔しく思うこともはるはずだと思うだけである。世の中でこの上なくすばらしい人であっても、心の深さをわからなくては、結婚しにくいと思う」と言う。
翁のいはく、~
翁のいはく、「思ひのごとくものたまふかな。そもそも、いかやうなる心ざしあらむ人にかあはむと思す。かばかり心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」。
翁がいうのは、「(私の)思いのとおりのことをおっしゃるのだな。そもそも、どのような気持ちがある人と結婚しようとお思いなのか。(五人の求婚者は)これほど気持ちが並大抵でない人々であるだろうに」。
かぐや姫のいはく、~
かぐや姫のいはく、「なにばかりの深きをか見むといはむ。いささかのことなり。人の心ざしひとしかんなり。いかでか、中におとりまさりは知らむ。五人の中に、ゆかしき物を見せたまへらむに、御心ざしまさりたりとて、仕うまつらむと、そのおはすらむ人々に申したまへ」といふ。「よきことなり」と受けつ。
かぐや姫が言うには、「どれほどの気持ちの深さを見ようと言うだろう。ほんの少しのことである。五人の気持ちは同程度であるようだ。どうやって、この(五人の)中での優劣がわかるだろうか。五人の中で、(私が)見たい物を見せてくださる方に、お気持ちが優っているとしてお仕えしようと、そのいらっしゃる人々に申し上げなされ」と言う。(翁は)「よいことだ」と引き受けた。