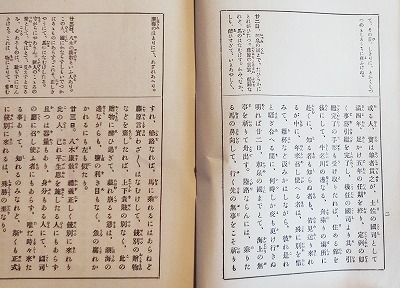〈問〉次の傍線部を現代語訳せよ。
灯のいと明かきに、御色はいと白く光るやうにて、とかくうち紛らはすこと、ありしうつつの御もてなしよりも、いふかひなきさまにて、何心なくて臥したまへる御ありさまの、飽かぬ所なしと言はむもさらなりや。なのめにだにあらず、たぐひなきを見たてまつるに、「死に入る魂の、やがてこの御骸にとまらなむ。」と思ほゆるも、わりなきことなりや。
源氏物語
現代語訳
灯火がたいそう明るいので、お顔色はとても白く光るようで、何かと身づくろいをしていらっしゃった、かつての現実の【生前の】ご様子よりも、嘆いても仕方のない様子で、(実際の)心がなくお臥せなさっているご様子が、いやになるところがない(くらい美しい)と言うようなことも、ことさらである。まったく普通でなく、類のない美しさを拝見すると、「死(の世界に)に入る魂が、そのままこの御骸にとどまってほしい。」と思われるが、(それは)無理なことであるよ。
ポイント
の 格助詞
「の」は、格助詞です。ここでは「主格」の用法です。

「体言+の」が、別の体言に係っていくのであれば、それは「連体修飾格」です。その場合、現代語の使い方と同じです。
「体言+の」が、用言に係っていくのであれば、それは「主格」です。その場合、「体言が~する」と訳すのが一般的です。
ここでは、「魂」という体言が、「とまる」という用言に係っていく構造なので、「主格」の用法であり、「が」と訳しておきましょう。
やがて 副詞
「やがて」は、漢字で書くと「軈て」です。漢字で書ける必要はありませんが、「軈」の「應」の部分に着眼してみましょう。「應」は常用漢字では「応」と書きます。つまり「応じる」ということです。
「やがて」という語のニュアンスは、「何かの出来事」対し、それに「応じる」ように次の出来事に進むということです。
そのことから、「やがて」は、時間的なものに使えば「すぐに」と訳します。
物体的、空間的なものに使えば「そのまま」と訳します。
ここでは、「 魂が → 御骸にとどまる 」という物体的な次元に使用していますので、「そのまま」と訳しましょう。
現代語では、「やがて」は、「少し時間が経ったあと」という意味で使用しやすい言葉ですが、古語では、前件と後件が直接つながっているさまを示す副詞です。
とまる 動詞(ラ行四段活用)
「とまら」は、動詞「とまる」の未然形です。
「止まる・留まる」は、「立ち止まる」「動きがやむ」「中止になる」「生き残る」「そのまま残る」「(心・目・耳などが)ひきつけられる」など、多様な訳し方をします。ここでは、「そのまま残る」の意味になります。

直後に「なむ」がありますね。
古文には、様々な「なむ」があるので、「なむ」を見かけたら、直前の語との接続によって識別する必要があります。
なむ 終助詞
「なむ」は主に次の4つの区別ができます。
① 未然形についている → 願望の終助詞「なむ」
② 連用形についている → 完了(強意)の助動詞「ぬ」+意志や推量の助動詞「む」
③ 消しても問題がない → 係助詞「なむ」
④ 「死・往・去」なむ → ナ変動詞「死ぬ」「往ぬ(去ぬ」+助動詞「む」

ここでは「とまら」が未然形なので、①の用法です。
未然形につく「なむ」は、主に「他者への願望」であり、「~してほしい」と訳します。

ここでの「魂」は、「亡くなった紫の上の魂」を指すと考えられますが、「与謝野晶子訳」では、「この自分を離れてしまうような気持ちのする心はそのままこの遺骸にとどまってしまうのではないかというような奇妙なことも夕霧は思った。」なっており、「正気を失った夕霧の魂が、紫の上の御骸にとどまろうとしている」といった解釈がなされています。

たしかに、どっちで解釈しても、意味はとおるね。